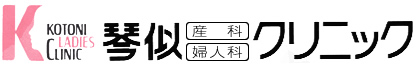最近の医療事情
記事一覧
クリックすると詳細が表示されます。もう一度クリックすると記事が閉じられます。
【 施設基準および加算に関する掲示 】
【明細書発行体制等加算】
当院では、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても無料で発行いたします。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
【医療情報取得加算】
当院では、オンライン資格確認について下記の整備を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています
・マイナ保険証を活用し、薬剤情報や特定健診等の診療報酬を活用した診療等が可能になります。
今後も正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
【基本診療料の施設基準に係る届出】
・有床診療所入院基本料6
【特掲診療料の施設基準に係る届出】
・婦人科特定疾患治療管理料
・一般不妊治療管理料
・HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
【 保険外負担に関する事項について 】
当院では、次の事項については実費負担をお願いしております。
診断書(当院規定)1通につき 3,300円
生命保険会社用診断書 1通につき 5,500円
産院用紹介状 1通につき 2,500円
診察券再発行 110円
妊娠検査(初診時) 6,000円
妊婦健診超音波検査 3,500円
低用量ピル(トリキュラー・マーベロン・アンジュ) 2,530円
低用量ピル(ラベルフィーユ・ファボワール) 2,200円
緊急避妊薬 9,900円
月経移動(9日まで) 2,200円
月経移動(10日以上) 3,300円
AMH検査 7,700円
ピル服用時血液検査 1,100円
帯状疱疹ワクチン(シングリックス) 20,000円
帯状疱疹ワクチン(弱毒生水痘ワクチン) 8,000円
子宮頸がんワクチン(シルガード9) 30,000円
診察券再発行 110円
院外処方箋再発行 660円
【 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について 】
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金とし医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
ただし、以下の場合は選定療養の対象外となります。
• 医療上必要があると認められた場合
• 後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合
後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
ビタミンDを十分とるだけで転倒する危険が減る?
高齢者になると、骨折が死亡と結びつく事があります。
特に骨粗鬆症があった上で骨折すると、死亡率が上昇する事が知られています。
骨折―寝たきり―生活の質の低下―死亡という経過をたどる事が多いようです。
骨折後の死亡率についても、いろいろな調査がありますが、男女とも50%位と考えられているようです。
心配なのは、死亡率の上昇は骨折直後だけではありません。
最近の研究では10年位危険な状況が続くというデータも出ています。
さて最近のトピックに、ビタミンDを十分にとると、転倒して骨折する危険だけでなく、転倒する危険そのものを減らす可能性があるというものがあります。
高齢者にとって、転倒しない事はとても大切です。
この調査が本当であれば、十分なビタミンDの摂取は高齢者の生活の質を上げる事が十分考えられます。
この場合食事でビタミンDを十分にとるというのではなく、ビタミンD剤を飲む事で、血液中のビタミンDの濃度を高くして調べたそうです。
その結果、ビタミンD剤を内服して高い濃度になった人は、そうでない人に比べて、約20%転倒するリスクが減ったそうです。
なぜビタミンDの濃度が高くなると転倒しにくくなるのかは分かっていませんが、興味のある研究である事は確かのようです。
今の所、対象の患者さんの数が少ない事もあり、これからのデータが待たれる所です。
またビタミンDを多量に、しかも長く薬の型で飲んでいると、長期的な副作用が無いかと言う問題も出てくるでしょう。
食事の中でビタミンDを多く摂る程度ではどうか等。いろいろな研究テーマが出てきそうです。
「うつ」とは診断されるけれど、意外と間違えられる時がある。
最近は、ストレスが多いせいか「うつ」あるいは「うつ症状」と言われる人が多いようです。
このため「うつ」的な症状のある人は、いろいろな科を受診します。
例えば婦人科に更年期障害では?と言って受診する人も多くなりました。
この傾向は各科とも同じ様です。
それは「うつ」でも、うつとは別の症状がメインで出てくる事があるからとも言われております。
例えば、不眠、めまい、頭痛、肩こり等。
神経科や心療内科の専門の医師が最初に診断すると、間違いは少ないでしょうが、専門医以外の所に行った時は、正確な診断がつきにくい時もあります。
実は、いま別な問題点もあげられてきています。実際は「うつ」や「うつ病」では無いのに「うつ」と診断される時です。
こうした原因の一番の理由は、やはり診察の時間の短さにあるとの事です。
通院していて、①症状が改善されない時、②薬で一時的に良くなった様に見えても、すぐ元に戻った時などは、再度医師とよく相談する事が必要なようです。
また早目に専門医を受診し、正しい診断をしてもらう事も大切です。
貴重な時間を無駄にしないためにも。
赤ちゃんは小さい時は何でも脳に行きます。母乳をあげているお母さんへのアドバイス
人間は血液―脳関門といって、食べて身体の中に入ったものが、簡単に脳に入り込まない様になっています。
脳の入り口に関所があり、そこで脳に安全なものだけが入るようになっているのです。
これは大切な脳を有害物質から守るためと考えられています。
ところが出生後約1年位は、この血液―脳関門が開いていると考えられています。
これには理由があります。この時期赤ちゃんの脳は大変に良く発達する時期で、たくさんのたんぱく質や糖分、脂肪等が必要とされると考えられています。
このため、この時期血液―脳関門がきっちり働き過ぎると、却って脳の発育障害を起こしてしまう可能性があるため、チェックなしで血液中の物質を脳に運び込む様になっているのです。
という事は、この時期のお母さんの食事がとても大切という事になります。まだこの時期のかなりの部分は、主に母乳を飲んで育ちますが、お母さんが食べた物は殆どフリーパスで母乳に出てきます。
母乳は、お母さんが赤ちゃんにとって悪いものは食べないという善意と信じてでてくるものです。
その意味でお母さんのちょっとした注意が大切です。
もちろん、ミルクで育てているお母さん、離乳食を食べさせる時期のお母さんも御注意を。
お母さん頑張って。
出産後のうつ症状は意外と多いものです
出産後のうつ症状は意外と多いものです。
早くに良くなる人もいますが、長く続く人もいます。お薬による治療など専門家による治療が大切です。
お産後にうつ症状が出てくる事はよく知られています。妊娠中を含めてマタニティーブルーとも言われています。
お産後のうつ症状は①数日から1~2週間で比較的早くに良くなる人 ②3ヶ月位で改善する人(約40%) ③1年以上つづく人(約30%)がいるという調査があります。
また症状が長くつづくかどうかという事と同時に、症状の重症度も問題です。
治療はお薬による治療を早目にすすめられたり、専門医との面接が大切なポイントの時があります。
早目の専門医―心療内科、メンタルクリニック、神経科、産婦人科―受診をおすすめします。
どうしたら良いか分からない時は、ご本人、家族の方だれでも良いですから、まずお産をした病院の医師と相談、適切な専門医を紹介してもらいましょう。
イギリスではお昼の給食が変わりました。子供の健康改善のためです
最近イギリスの学校給食の内容が大幅に変わったというニュースがありました。
給食の中に野菜を多く摂りいれるという事だそうです。これには背景があります。
例のサッチャー首相の民営化政策の中に学校給食も入っていました。
その結果、生徒達の好みそうなものだけが売られるようになり(コーラ、フライドチキン等)、生徒の肥満、メタボリック症候群予備軍が増える結果になったそうです。
これを心配した、ある有名なシェフが「これではいけない、成長期にはそれに合わせた食事を」という提言をして、今回の改善になったとか。
今までの食事に慣れていた生徒には不満があるそうですが、その成果は時間が経ってきっと出てくるでしょう。
それにしても1人の勇気のある人に関心します。またそれを受け入れた政治にも敬意を表したいですね。
運動は年をとってからも効果がある。認知症、骨折、心臓そして寿命
運動をすると健康に良いというデータが相次いでいます。
注目すべき点は、若い頃から行う事も有効ですが、年をとってから始めてもその効果が確かめられている事です。
例えば55歳以上の人 3,903人を対象にした調査では、調査開始時点では418人に認知障害があったそうです。
その2年後には、残り3,485人中207人に認知障害が発生したそうです。
この中で調査開始時に①運動をしない人グループ、②中等度に行うグループ、③高度に行うグループに分けてみると、この2年間に新しく認知症になった人は、①13.9%、②6.7%、③5.1%で、運動をした人としない人に差があったそうです。
また運動する量によっても認知症発生率に差が出たという事になりそうです(ミュンヘン工科大学)。
この他運動すると転倒する率が減り、骨折する率が減るという調査もあります。
さらに60歳(平均年齢)の時の運動レベルを調べておき、その後の健康状態をみてみると、70歳以上になった時は、60歳の時点で運動をしていた人の方が、①慢性の病気になる比率が低かった。②心臓手術を行う率が低かった。③認知障害や精神障害の比率が低かったそうです(ハーバード大学)
運動する事は唯一がんの予防になる事も知られています。
これらを含めて考えると、運動する事は身体に良い事ばかりのようで、運動を開始するのに遅すぎるという事はなさそうです。
自分のペースに合った所からで良さそうですが、まずは運動を始めてみませんか。
チェロは男性?女性?
日本語にはそういう言い方はありませんが、ヨーロッパでは男性名詞、女性名詞があります。
ところが同じ楽器でも国によっては男性名詞の時も女性名詞の時もあります。
チェロもそうです。
ロシアでは女性名詞、フランスでは男性名詞だそうです。
名チェリストであるロストロポーヴィチはかつてなぜチェロを選んだか聞かれた時に、こう答えたそうです。
「チェロは女性名詞でしょ、だから、女性を好きになるように、好きになったんですよ。
ただね、何年もたってから分かったんですけど、フランス語じゃ、チェロは、男性名詞なんですって。ほんとに、ぞっとしましたよ!もし、音楽に興味を持ち始めた頃にそのことを知っていたら、僕がどんな楽器を選らんかだかは、わかりません」
ロストロポーヴィチ
アレクサンドル・イヴァシキン
秋元 里予 訳 春秋社
やっぱりカルシウムの摂取は骨折予防になる。
将来の骨粗鬆症の予防は大切な事です。
ある年令以上の人が大腿骨の骨折をすると、寝たきりなる確率が高くなるという研究があります。
年をとってから長い事寝たきりになるのは、やはり嫌ですね。
女性の場合女性ホルモンが十分に出ると、骨塩量の低下を予防し、その結果骨折を予防出来ます。
ホルモン補充療法などはその延長上にありますが、最近ホルモン補充療法の欠点も指摘されるようになり、一時に比べるとホルモン剤の使用量が減ってきている感じもします。
ところで以前から使用されていたカルシウム剤やビタミンDは、どうやらこの骨粗鬆症の予防になる事を確かめる研究がいろいろ出ています。
ビタミンD単独よりもカルシウム+ビタミンDが良いとか。
またカルシウム単独でも良さそうだという研究があります。
ただビタミンDは最近がんの予防になる事でも注目されています。
カルシウムとビタミンDをとる事は試してみるべき事かも知れません。
因みにカルシウムの多い食材は
干しエビ モロヘイヤ ヨーグルト
イワシの丸干 ダイコンの葉 牛乳 煮干し 菜の花
がんもどき 豆腐 シシャモ 利尻昆布
ビタミンDの多い食材は
ニシンのくん製 ピータン アンコウの肝 白きくらげ(乾) 紅サケ きくらげ(乾)
イワシの丸干 ウナギ蒲焼 シラス干
子宮体がんの診断は1回だけでは分からない時がある。
最近子宮体がんの人が増えています。
子宮がんのうち40%は子宮体がんと言われています。
また子宮頸がんと同様、若い年代にも増えつつあるようです。
しかしその子宮体がんの診断は実は、むずかしい事が分かっています。
通常の健康診断では、子宮の奥を採る細胞診検査が行われます。
これで異常が見つかると、子宮の中に癌やいわゆる前癌状態がないか組織検査が行われます。
細胞診検査自体も判定がむずかしいのですが、本来精密検査であるべき組織検査も正確な診断が困難な時もあります。
がんの進行度にもよりますが、組織検査の精度が35%(3人に1人)しか無かったという調査もあります。
こうした事を考えると、早く正しい診断を受けるためには、
1.定期的な検診をうける事
2.不正な出血があった時は、ためらわずに検査を受ける事。
3.細胞診や組織検査以外にもすすめられたら超音波で子宮の厚さのチェックを受ける事。
4.MRI等も役に立つ事があり、これらの検査も提案されたら受ける事。
など、きめ細かな検査を受ける事が必要な様です。
今の所、検査の正確度を上げるための努力がいろいろ行われている所です。
母乳は成人した後の心臓血管系の病気の確率を低下させるらしい。
米国の心臓協会での発表データの中に、母乳で育てると、成人後心血管系の病気のリスクが低くなるという注目すべきものがありました。
これは母乳で育った人と、ミルクで育った人を調べたものですが、母乳で育った人の方が、将来HDL-コレステロール(善玉コレステロール)の値が高くなること、BMIの値(肥満の目安になる値です)が低くなるのが分かったそうです。
これらは、いずれも心臓血管系の病気、例えば狭心症や心筋梗塞の発生を抑える事が分かっています。
このため母乳で育てた方が、将来子供の長期的な健康状態に良いと考えられると言えそうです。
発表した人は「これらの状態(心血管系の異常)は一生つきまとう疾患だけれど、そのルーツは人生の初期にある事が示された」と言っています。
ただ何故母乳保育にそのような力があるのか、どの程度つづければ効果が出るのか、長くつづけて却って悪い事はないのか等についてはまだまだ解明されていません。
これからの研究の効果が注目されます。
働き過ぎはやはり身体に悪い!まずは心臓のデータから。
働き過ぎは身体に良くない事は、何となく分かっています。
脳や心臓の血管に対する負担も大きくなりますし、ストレスが重なるとがんになり易いというデータもあります。
最近労働時間と心臓の病気の関係についてのデータが出ましたので、お知らせしておきましょう。
世界で最も読まれている医学誌の1つに出ていた論文です。
ロンドンの公務員を対象とした調査ですが、元々心臓の血管に異常のない人7,095人を10年以上に渡って追跡したものだそうです(平均12.3年間の長さです)。
平均年齢 48.8歳
男性 70.3%
年齢、性別、総コレステロール、喫煙の有無等、心臓病に関するいろいろな要因を考慮に入れた上で正確なデータ処理をした所、以下の様な結果が出たそうです。
まず日頃どの程度労働したかグループを分けました。
① 7-8時間のグループ、
② 9時間、
③ 10時間、
④ 11時間以上、
その結果平均12.3年間の間に死亡に至らない心筋梗塞の人が163人、心血管死の人が29人出たそうです。
平均労働時間が7-8時間の人を基準とすると、11時間以上働く人は、1.67倍危険率が上がったとの事です。
やはり働き過ぎは身体に良くない事は確かめられた事になります。
これに仕事の内容(例えば常にストレスがかかり過ぎている等)を加えると、この危険率はまだ上がるかも知れません。
さらに、心血管の病気の他、脳血管の病気、肝臓や腎臓の病気、うつ等の精神的な病気、がんの発生等を考えると、病気になる確率はますます高くなると考えられます。
働き過ぎないようにする事が何より大切と言えそうです。
高齢者は歩くスピードで寿命が違う
いろいろな運動をすると、健康に良い事は知られています。
今はウォーキングも十分な運動療法として認められていますが、同じ運動でも、少し脈拍が増える程度でも良いとされています。
少し脈拍が上がる程度?と言っても少し難しいですね。1つの目安に歩く速度があげられます。
ここで最近興味深い調査について一言。
高齢者の歩行速度を測ってみると、速く歩く人の方の寿命が長い事が分かったそうです(BMJ誌)。
これは高齢者に6mの距離を歩いてもらって、その速度を調べ、その後の死亡との関係を調べたものです。
その結果、歩く速度を3つのグループに分けて判定した所、歩行速度が最も遅かったグループの人は、最も歩行速度の速いグループの人に比べ、約1.5倍死亡率が高かったそうです。
死因別でみると、歩行速度の遅いグループの人、心臓血管の異常で死亡する人が約3倍多かったそうです。
歩行速度が遅いグループの人は、いろいろな病気がある場合があり、それも原因の1つになる事があるかも知れません(例えば脳卒中の後遺症や、大腿骨の骨折など)。
しかし、もし歩けるなら、なるべく歩く事。しかも少し速く歩く事はいろいろメリットが多い可能性があるでしょう。
勿論若い頃から、この事に心掛けるとよりメリットが上昇すると思われます。
一方で高齢の方が、あまり速いスピードで歩く事を考えると、却って転倒などの危険がある時もあります。注意しながら…という事でしょうか。
フランス人とドイツ人では赤ちゃんの泣き方からして違う!
生まれたばかりの赤ちゃんの泣き声にも個性がある事は知られています。男女差もありそうです。
しかし最近、とても面白い事実が明らかになってきました。
どうやら国によって赤ちゃんの泣き声に差があるらしいのです。
と言っても、今の所フランスとドイツ人の間の比較だけですが…。
フランスの新生児(生まれたばかりの赤ちゃん)は尻上がりに声が高くなり、ドイツの新生児はその逆だそうです。
これは両国の新生児の泣き声を集めて分析した結果ですが、その理由として両国の言葉の違いがあげられているようです。
フランス語とドイツ語は音調が全く違って、フランス語は語尾を強く発言する傾向があるのに対し、ドイツ語は語尾が低くなる傾向があるとの事です。
そう言えばボンジュール(↑)ですし、グーテンターク(↓)ですものね。
お腹の赤ちゃんの聴覚は比較的早くに発達する事が知られています。
一説によると4ヶ月位から、発音のパターンを記憶し始めると言われています。
これまでも、赤ちゃんはお腹の中にいるうちから、お母さんの声を聞き分けている事は知られています。
お父さんの声はあまり記憶がなくても、お母さんの声は羊水を通じてよく理解する事。
お母さんの怒った声や叫ぶ声は嫌がる等いろいろな重要なデータが出ています。
しかし今回この様に、生まれたばかりの赤ちゃんの泣き声に、お母さんの言葉の影響が表れるという事がはっきり分かったという事は、とても重要な事と言えるでしょう。
あまり気にし過ぎてもいけませんが、お腹の赤ちゃんには、「安心できるお母さんの声」が必要なようです。
妊娠中の体重増加の目安-もともとの体重からの増え方が問題
妊娠中の体重増加には、注意が必要な事はよく知られています。
適切な体重の増加が望ましいですね。
さて先日産婦人科の専門誌にこの様な調査が出ていました。
お母さんの体重増加は一律に制限を設けるのではなく、もともとの体重を問題にすべきだと言う事です。
これはもともと体重が少ない人は妊娠中に体重が多少増えても良いが、肥満気味の人は、体重の管理が大切だと言う意味です。
だいたいの目安として次のような数字をあげています。
妊娠前のBMIが 20-24.9の女性は 2.3-10.0㎏まで
〃 25-29.9の女性は 9.1㎏未満
〃 30以上の女性は 5.9kg未満
との事です。
BMIとは、体重(kg単位)÷身長×身長(m単位)
妊娠中の皆さんの参考になれば…。
HPV感染が長いとがんになる可能性が高くなる?
子宮がんとHPVの関係は、ほぼ間違いないと考えて良いでしょう。
性行為のある女性の80%は、一度はHPVの感染があると考えられています。
一方でHPVに感染した場合90%の女性は、ほぼ1-3年間でウイルスが消失すると考えられています。
ただこのHPV感染の消える期間は年齢によっても変わるようですし、感染したウイルスの種類、感染した人の抵抗力も関係するようです。
また別な考え方もあります。
将来がんになる可能性のあるHPVの感染期間は平均8ヵ月、がんにならないHPVの感染期間は平均4.8ヶ月というデータがあります。
ところで、HPVに感染した場合、どの位ウイルスがいると癌になるかは分かっていません。しかし、どうやら感染期間が長い程、がんになる可能性が高いそうです。
今の所いわゆる前がん状態や、子宮頸がんにまで進行するには、数年間の持続的な感染が必要との考えがあるようです。
しかし実際感染が確認されても、どの位の期間HPVの感染が持続しているかを調べるのは、そんなに手軽ではありません。
1つはHPVの検査を定期的に行う方法があります。しかしこれはなかなか大変です。
もう1つは、細胞診の検査をつづける事です。こちらの方はHPV検査をつづけるよりは安易でしょう。但し細胞診でHPVの感染を正確に推測することは不可能です。
細胞診や組織診で異常が長くつづく時は、HPVの再検査をする事が必要になってきます。
子宮内膜症と痛み
子宮内膜症にはいろいろな症状があります。
痛みもその1つですが、子宮内膜症がありながら痛みを我慢している人も多いようです。
子宮内膜症自体は非常に多い病気ですが、実際に婦人科の検診をうけている人は少ない(10数%)という統計もあります。
生理痛の強い人は、むしろ我慢せず、早目に婦人科を受診し、適切な治療をうけた方が良いと考えられています。子宮内膜症もほかの病気と同じく、早くに治療した方が効果的と考えられるからです。
さて子宮内膜症があって生理痛が強い時はいろいろな治療法がすすめられます。
しかしこれには手順があります。
1)実際に子宮内膜症があるか。
2)あるとしたらどの程度か。
これを病気の進行度といいます。
当ネット、婦人科の病気:子宮内膜症を参考にされると良いでしょう。
3)その程度に応じて、どんな治療が適切かという事が検討されます。
治療法については数多くの方法があります。
例えば低用量ピル、ディナゲスト、ダナゾール等の内服薬、スプレキュア、ナサニール等の点鼻薬、さらにリュープリン等の注射薬もあります。ホルモン剤入りのリング(ミレーナ)もよく使われるようになっています。
さらに症状が強い時は、腹腔鏡を利用した手術がすすめられる時もあります。
ところで治療終了後に再発が起こり易いのも子宮内膜症の悩みです。
薬や手術を合わせた治療後、痛みの再発率は約60%という調査があります。しかし逆に言えば、きちんと治療すると約40%の人は再発が無いという事になります。
特に手術による治療はかなり効果がありますが、それでも半年後には約45%の人に再発があるという調査があります。
最近、手術に引き続き、薬を内服する事が多く再発率が低くなる事が期待されています。
定期的にピルを内服したり、長期使用に耐えられるディナゲストが採用される事が多いようです。
「子育て」ホルモンと「抱っこ」ホルモンって知っていますか?
出産後母乳が出て赤ちゃんが吸ってくれる、という一連の動きの中には、お母さんのホルモンの働きが大切になります。
この働きに重要なホルモンが2つあります。2つとも脳から出るホルモンで、1つはプロラクチンというホルモン、1つはオキシトシンというホルモンです。
プロラクチンは母乳を作り出すホルモンですが、このホルモンの働きによって、お母さんは自分の子供に関心を注ぎ込むのだそうです。このためこのホルモンを「子育てホルモン」とも言うそうです。
一方オキシトシンはお産後に脳から出てきて、赤ちゃんがおっぱいを吸うと、母乳が出るように働きます。このホルモンが沢山出ると、お母さんは、「相手と協調しやすくなったり」「穏やかな気持ちになれる」「ストレスに対して強くなる」そうで、このホルモンを「抱っこホルモン」とも呼びます。
2つのホルモンとも赤ちゃんにとっては、なくてはならないものですが、お母さんにとっても大事なホルモンになるようです。
その証拠に授乳をすると、産後少しうつ気分になっていた人が改善してくるそうです。
授乳する事自体が逆にお母さんの気分を和らげ、お母さんの為になっているようです。
子宮体がん検診をうけましょう-その1-
子宮がんには①子宮頸がんと②子宮体がん があります。この2つはともに子宮に出来るものですが、お互い何の関係もありません。
①子宮頸がんは若い女性に多く見つかるがんで、HPVというウイルス感染が原因です。
これに対し、子宮体がんは50代に多く(次は60代)、比較的年配になってから見つかるがんで、ホルモンのバランスの崩れが原因とされています。
ただ、最近他のがんと同様、子宮体がんが若い女性に増えてきているという傾向はあるようで注意が必要です。
年齢が偶数の時、自治体から子宮頸がんも子宮体がんも一緒に2100円で検査を受けられるというシステムがあります。事前の手続きは不要です。
40歳をすぎた方、不正出血のある方は子宮体がん検診を受けるようにしましょう。
さてこの2つのがんは、どちらが多いと思いますか。
実は子宮頸がんより、子宮体がんの方が多いのです。さらに40歳以上になったら明らかに子宮体がんの女性が増えてきます。
しかし40~50代の女性が子宮がん検診に行っても、子宮頸がんの検診を受けるだけで、子宮体がんの検診をうけない方が結構多い事が分かっています。せっかくの子宮がん検診でも、これでは片手落ちですね。
子宮頸がんより多い、しかも最近増えている子宮体がんの検診を受ける事が大切です。
子宮の奥の方(子宮体部)に検査の器具が入るので少し痛いのですが、痛みとしては大した事がありません。
次回はその検査の事を。
子宮頸がんは40歳代以上でも増加
子宮頸がんは世界的に見ると減りつつあるがんです。
しかし日本では決して減っていません。むしろ死亡率が上昇しているがんです。
特に20歳代から30歳代前半の若い女性の子宮頸がんが急激に増えており、その増加率は、この20年間で約2倍強になってしまいました。
これをもう少し詳しく見てみると、1999年位までは、子宮頸がんになる女性は人口10万人当り7人位でほぼ一定しておりました。
ところが2000年を境に急に子宮頸がんに罹る人が増えてきております。
2011年では人口10万当り17人位と、1999年以降に比べると2倍以上となっています(国立がん研究センター がん情報サービスから)。
日本では1年間に約1万人の女性が新たに子宮頸がんと診断されています(3000人が亡くなっている。
このデータからは、早急に若い女性のがん罹患を止める事が必要と判断されます。
さて、ところでもう1つ問題があります。
若い女性程ではありませんが、40歳代以上の子宮頸がんの女性も少しずつ増えている事です。
以前、1990年代は40歳代以上の女性の子宮頸がんは多かったのですが、その後徐々に減り始めました。これは世界に先駆けて、日本で子宮頸がん検診が広まったお陰と考えられています。がん予防に検診が効果があると分かった、いわばモデルとも言うべきデータでした。
ところが、40歳代以上の女性の子宮頸がんが最近少しずつ増える傾向があります。
2008年頃からその傾向が出てきており、最近は2007年以前に比べると30-40%程度増えているという調査があります。
さて子宮頸がんの予防は何と言っても、HPV予防ワクチンです。
現在は若い女性の子宮頸がん予防ワクチンは、副作用の点から積極的な投与が避けられる傾向があります。
それならば、痛みにもある程度耐えられ、自分で投与の可否が決心出来る成人女性からワクチン投与を始めてはいかがでしょうか。
現在日本ではHPV感染予防に2価ワクチンと4価ワクチンが許可されています(それぞれ2種類と4種類のウイルスに効果があります)。これだけでも十分効果が期待されていますが、世界では9種類のウイルスに効果のあるワクチンが使用され始めています。
これらが広く使用されると、ワクチンを投与している国では、子宮頸がんが消える可能性があるとの予測データがあるそうです。
効果、副作用を含めて議論が広まるのが望まれます。
私見ですが、よく情報を広めて、まず希望する女性には用いる、しかし希望しない人には勧めないという立場でワクチン投与を考えるのはどうでしょう。
子宮内膜症とダイオキシン
身体に取り込まれたダイオキシン量と子宮内膜症の重症度が関連しているという研究があります。もともとダイオキシンと子宮内膜症の関係は推測されていましたが、最近改めてその関係を表す調査結果が出ました。(M.A.Martineg-Zamoraら.Human Reprod.2015) 彼らは深部浸潤性子宮内膜症のため腹腔鏡下手術を受けた30名の女性のグループと、対象として子宮内膜症ではない病気で腹腔鏡下手術を受けたグループを選びました。これらの2つのグループの患者さん達から手術の時に、お腹にある大網から1-2gの脂肪を採取し、ダイオキシン様物質の測定を行っています。 その結果深部浸潤性子宮内膜症のグループでは総ダイオキシンレベルとPCBレベルがコントロール群に比べ、明らかに高かったそうです(統計学的に有意差があった)。PCBの中には、発癌性のあるPCB-126という物質も含まれていたとの事で、子宮内膜症の重症度とダイオキシンの関係が大きい事がますます分かってきました。子宮内膜症の中に悪性なるタイプがありますから、これもダイオキシンが関係している可能性があるかも知れません。 さてダイオキシンと言うと、どこから人間の身体に入ってくるのかが次の問題になります。イメージとしては、ゴミの焼却等の際に出てくると思えますが(プラスチックなど)、ダイオキシンの摂取はまず①大気、②水、③土、④そして食品です。 特にマグロには相当の濃度が検出されるそうです。また魚の油の成分なども多いとされており、日頃の食事の管理も大切なようです。
帝王切開で生まれた赤ちゃん-糖尿病と喘息の発生をみてみると-
一口に帝王切開と言っても2種類あります。
1. はじめから帝王切開を予定していた人
前回帝王切開の人、逆子、明らかに骨盤の狭い人など、
これを選択的帝王切開といいます。
2. 一方、はじめは下からお産(経腟分娩といいます)をする積りだったのに、何らかの理由で、帝王切開になった人
こういう人はある程度陣痛の経験をする事が多いようですが、これを非選択的帝王切開といいます。
最近、はじめから選択的帝王切開手術を受けた人、非選択的帝王切開手術をうけた人、経腟分娩だった人から生まれた赤ちゃんに、将来何らかの病気になる可能性がないかという調査が行われました(JAMA 2015)。
それによると
1.選択的帝王切開手術で生まれた赤ちゃんは、Ⅰ型糖尿病になる確率が高い可能性があった。(但し、このデータは統計の間違いがあるかも知れないとの事です。)
2.経腟分娩で生まれた赤ちゃんは、選択的帝王切開手術で生まれた赤ちゃんに比べ、喘息になる確率が低いという事でした。
これは生まれてくる時にお母さんの体内にある細菌に触れる可能性があり、これが喘息予防になるという推論があるそうです。
これらのデータは、まだまだ時間をかけて症例を集め、正しい結論を得なければなりません。
但し、どうしても選択的帝王切開を受けなければならない人以外、陣痛を一度経験する事は悪い事ではないという考えもありそうです。
子宮頸がんが急に増えた理由 それは1999年に起った出来事がきっかけ!
日本で若い女性の子宮頸がん患者さんが増えています。これは欧米と逆の傾向で、憂慮すべき問題となっています。
また子宮頸がんではないものの、その前段階である異形成上皮という異常も増えています。
最近の調査では、毎年新たに子宮頸がんに罹る女性は、人口10万人あたり17人程度で、その比率がだんだん上がってきているのが分かっています。
さて、この子宮頸がんの罹患率を見てみると、1999年までは人口10万人あたり7人の発生率で、その比率はほぼ一定でした。しかし2000年を境に急に子宮頸がんの女性が増えています。
そこには何か理由があるのでしょうか。
実はその前年の1999年に大きな出来事がありました。
日本でのピル解禁です。
子宮頸がんはHPVというウイルスの感染が原因の病気です。それまで避妊のために用いられていたコンドームが使われなくなったのが、子宮頸がん患者さんの増加と関係がありそうです。
確かにピルは、避妊法としては確実ですし、女性が自分の意志で避妊出来るという事で利点があります。
かなりの女性が避妊のためにコンドームからピルに替えた可能性があります。
事実コンドームの販売量も1999年から減ってきています。
どうやらコンドームが子宮頸がん増加の「キーポイント」になっているように思えます。
ところでまだ幾つかの問題点が指摘されています。
最近梅毒に罹る人が増えている事です。これは最近たびたびマスコミでも報道されています。梅毒は一時大幅に減っていた病気で、新しい感染者を診察した事が無いという医者もいる位です。
この病気が増えてきているのは、これまたコンドームの使用と関連がありそうです。
クラミジア感染の方が増えている事も考えると、コンドームの使用について、改めて考える必要がありそうです。
がんは高温に弱い 温熱療法の効果が上がっています
温熱療法というがんの治療法があります。がん細胞と正常の細胞を比較すると、がん細胞は高い温度で死滅してしまうのですが、正常細胞は耐えて生き残るというものです。
例えば42℃ではがん細胞は死んでしまいますが、正常の細胞は耐えます。
この考えから言えば、がんのある部分だけを高い温度にすると、がん細胞だけ死ぬ可能性があるという事になります。
この考えを利用した治療法-がんの温熱療法といいます-は年々進歩しています。
この治療法を研究するハイパーサーシア学会も28回目となりました。
2011年の学会でも、いろいろながんに温熱療法が効果があった事が示されていました。
例えば肺がんの中の非小細胞肺がん(NSCLC)というタイプの人を対象にした調査では、進行したタイプであるⅢ期がんやⅣ期がんでは、抗がん剤治療や放射線治療に温熱治療を一緒に行うと治療効果が上昇したそうです。(但し、転移の部位によっては治療対象外になった人がいます)。
Ⅲ期の患者さんでは、完全奏効(CRといいます)41%、部分奏効(PRといいます)48%、安定(SD)11%だったそうです。
CRとPRを合わせると89%の人に効果があったと考えられたそうです(筑波大学、今田肇教授らの発表データから)。
この治療法では直接温度を上げる事が出来る所に器具が当たらなければなりません。
一方で温熱が十分に行き渡る部位に出来たがんには、これからの効果が期待できる治療法と言えるでしょう。
今後
①器具の改良でいろいろな所のがんに温熱が行くようにする事。
②温熱の温度や照射時間の検討。
③他の治療法との併用。
などで治療の発展が望まれるのではないかと考えられます。
非小細胞肺がん(NSCLC)についての情報をもう1つ。
日本でのがんの死亡率とは少し違い、アメリカの女性のがんで亡くなる人は肺がんが第1位です(男性も)。
今後平均余命が延びる事から、高齢者の肺がんが増える事が予想されています。
しかしこれまでは、高齢者の肺がんに対する治療法は、もし抗がん剤を使用するとしたら限られた方法しかありませんでした。
最近平均年令77才の患者さんを対象に、カルボプラチンという薬剤とパクリタキセルという薬剤の合剤を飲み、今まで治療を受けていた人(一種類の抗がん剤しか使われなかった人)と比べてみると、2つの薬の合剤を飲んだ人の方が一年生存率は45%、今までの治療だと25%と、薬の種類が多い人の方が効果があったというという事です(Elisabeth Quoix lancet 2011)。
2種類の抗がん剤が使われる訳ですから、白血球の数が減る等の副作用は強くなるそうです。
前の温熱療法に加えて、1つのがんについても、世界中で研究が進んでいます。
がん細胞を死滅させる、がんになっても亡くならないという時代が早く来る事を願っています。
サウナが心臓に良いらしい
最近の研究でサウナが健康に良いとのデータが出ていました。
サウナが本場のフィンランドからのものですが、サウナを利用すると心臓突然死、心筋梗塞などの心血管の病気、全死亡の率が少なくなったそうです。
しかも、その病気になる確率はサウナを利用する機会が多いほど、また入っている時間が長いほど低くなるとの事です。
このデータは、世界で最も読まれている医学雑誌の1つであるJAMAに発表されたものです(2015)。
フィンランド人2,315人を長期間(平均20.7年)調べたもので、サウナ浴①週1回群、②週2-3回群、③週4-7回群に分けて検討しています。
その結果、心臓突然死は、①10.1%、②7.8%、③5.0%、心筋梗塞などの心臓の血管疾患による死亡は、①14.9%、②11.5%、③8.5%、全死亡率は、①49.1%、②37.8%、③30.8%とそれぞれサウナに入る回数の多い人ほど死亡率が低かったそうです。
一方、サウナに入っている時間も、全死亡率以外は、死亡率と関係したそうです(11分未満、11-19分、19分以上で比較)。
研究者は、なぜそうなるかの解明には至っておりませんが、心臓死とサウナの効果については確かな結論を得たようです。
さて日本人はフィンランド人のようにサウナに入る習慣はあまり多くありません。
このため、このデータが日本人に当てはまるかどうかは分かっていません。
しかし日本人の好きな銭湯、温泉あるいは入浴そのものは、健康に良い影響を与える可能性があると考えます。
抗がん剤治療中の人は魚に注意
最近健康志向が高まり、健康を維持したい人は、食品にも拘りを持っているようです。
特に肉より魚、魚の中でも青魚が健康に良いとの情報が広まっています。
ところが最近、抗がん剤の治療を受けている人は、ニシンやサバなどの脂肪の多い魚、あるいは魚油を中心としたサプリに気を付けた方が良いとのデータが出されています( JAMA 2015)
オランダのがんセンターからのデータです。
最近抗がん剤としてよく使われる白金の入った薬(シスプラチンが代表的なものです)は、身体から分泌される脂肪酸で、その抗がん作用が落ちる事が分かってきました(動物実験)。
今回の調査では、まず抗がん剤を用いている人に、EPAやDHAといったn―3脂肪酸の入ったサプリメントを常用しているか聞いたところ、常用者は11%との事でした。
次に魚油サプリメント(EPAやDHAの入っている)、4種類の魚(ニシン、サバ、マグロ、サケ)の脂肪酸を測定してみました。
その結果ニシンとサバは脂肪酸を高度に含んでいましたが、マグロ、サケでは脂肪酸が少なかったそうです。
一方魚油サプリメントには脂肪酸がたくさん含まれていたというデータでした。
これらの結果から、抗がん剤の治療を受けている人は、ニシンやサバなどの油の多い魚、あるいは魚油のサプリメントを摂る抗がん剤の効果が落ちる可能性があるとしています。
これらの事から研究者たちは、今回の調査が確定的なものではなく、将来否定される結果が出るかもしれないが、しかし今後新しい見解が出るまでは、抗がん剤治療中の人は、魚油の多い魚を食べない方が良いと伝えています。
鎮痛剤の貼り薬に注意が必要になる?!
最近アメリカの食品医薬品局(FDA-アメリカで食品や医薬品の有効性や安全性の管理、情報の発信をする組織)から、重要なデータがでました。
これはNSAIDと言って非ステロイド系の消炎剤についての注意情報です。
フルルビプロフェンを含む薬ですが、消炎、鎮痛の貼り薬として日本でも沢山使われています(薬品名はネットをご覧ください)。
薬局でも市販薬として売られていますから、知っている人も多いと思います。
さて、この薬剤を使用した人のペットのネコが死亡したと言う情報です。
飼い主は当然ペットに貼り薬を使ったわけではありません。
人間が使っていたのに、ペットが死亡したのだそうです。
しかも獣医さんが解剖をしたところ、腎臓や腸にNASIDの中毒とみられる異常が見つかったとの事です。
ネコが死ぬ前の症状として、食欲不振、無気力、嘔吐、血便などがあったと伝えています。
FDAもどうして薬剤の成分が、ネコに入ったのかの分析はしていません。
ただし、ペットの飼い主には、薬がペットの手の届かない所に置く事を勧めています。
また、薬を塗った個所を覆ったほうが良いか担当医と相談しなさいと言う事です。
しかしこの問題はまだまだ議論されなければならない所がありそうです。
ネコより大きな犬だったらどうか。小さいペットに先に症状がでて、大きなペットは後から症状が出て来る事もあり得るでしょう。
何より小さなペットには短時間で異常な副作用がでるが、より大きな人間に、将来時間をかけての異常が出て来る可能性だって考えておく必要があります。
よくよく注意が必要になるでしょう。
アメリカに比べ、日本でがんが増えている?!
米国がん協会(ACS)が2015年版のがん統計を発表しました(CA Cancer J.Clin.2015)
この統計は過去の各種のがん登録や死亡を調べ、その年のがんのいろいろなデータを予測するものです。
それによると、2015年アメリカでは165万8,370人に新たにがんが見つかり、58万9,430人ががんで死亡するとの事でした。
これに対して、日本では4月28日国立がんセンターの発表があります。
2015年に新たにがんと診断されるのは98万2,100人、がんで死亡する人は37万900人との予測だそうです。
因みに2013年がんで死亡した人の実数は、36万4,872人(男性216,975人、女性147,897人)でした。
人口をみてみると2011年でアメリカは約3億1,000万人、日本は約1億2,700万人です。人口の割合から言えば、がんに罹患する人も、死亡数も日本の方が高いと言えます。
さて、またアメリカのデータに戻ってがんの推移をみてみましょう。
2007年~2011年の5年間で、がんの罹患率は男性で1.8%減ったのに対し、女性は不変でした。
一方で、がんを原因とする死亡率は男性1.8%、女性1.4%低下していたそうです。
注目されるのは、アメリカでがんの死亡率が最も高かったのが1991年だったそうで、それが2011年には22%も低下していたとの事です。
がんの種類別では、肺がんの死亡率が男性で36%、女性で11%の低下。乳がんは35%以上、大腸がんは47%低下していたとの事でした。頼もしい話です。
ACSはがん死亡率低下の要因は早期発見が進んだ事、治療技術の向上の効果としています。
この様に、がんの死亡率はアメリカでは1991年を境に減ってきているのに対し、日本では逆に増え続けています。
統計のある1947年から、がんの死亡率は一貫して上昇しています。1991年(アメリカで最も死亡率がピークに達した年)に比べると、最近では何と1.6倍に増えてしまいました。
アメリカで22%減ったがんが、日本で60%増えた理由をしっかり検証しなければならないでしょう。
日本でがんで死亡する人が増えているのは、日本人の年齢構成に原因があると信じられています。
しかし、それではアメリカで減ってきているがんの死亡率が、日本で増えてきている事が説明できません。アメリカでも高齢化は存在するのですから。
これらについては、さらに深い議論が必要になるでしょう。
新しいHPV予防ワクチン
子宮頸がん予防ワクチンは現在日本で様々な議論を呼んでいます。
そんななか厚生労働省は積極的なワクチン接種の奨めを控えているようです。
さて、アメリカの食品医薬品局(有名なFDA…薬や食品の安全性を議論し許可する機関)は、2014年12月新たなワクチンの使用を許可しました。
これまで子宮頸がん予防ワクチンは、HPV16型、18型に効果のあるものと(2価ワクチン)、これに加え尖圭コンジローマの原因になる6型、11型を対象にしたワクチン(4価ワクチン)が世界中で使用されていました。
しかし、今回9つの型に効く9価ワクチンが許可される事になりました。
子宮頸がんの原因になるウイルスは全部で13種類あると考えられています。
今回の9価ワクチンは、、従来の16型、18型に加えて、31、33、45、52、58の5つの型と尖圭コンジローマの原因になる6型、11型の9種類のウイルスに効くとされています。
今回ワクチンの効用と副作用を調べるために、アメリカを含む多国間で臨床試験が行われたそうです。16-26歳までの女性1万4,000人を対象にして調べた結果、有害だったという事象は、痛み、腫れ、発赤、頭痛が指摘されていました。
効果については、今後長期間の経過みて判断される事になります。
予測通りこの9価ワクチンが有効に働く事が証明されれば、子宮頸がんの90%が予防出来るとの考えがあります。日本人に多いとされる16型、18型、52型、58型がカバー出来ることになります。
但し日本でもワクチンの治験が行わなければ、日本での使用はずーと先になるでしょう。
理論上、今後HPV予防ワクチン投与が確実に広まれば、子宮頸がんがなくなる日も考えられます。
日本人の年間子宮頸がん患者さんが約1万人、亡くなる人が年間約3,000人弱です。
ワクチンを投与する事で、子宮頸がんを予防し、年間3,000人弱の女性の命を助けるか、副作用を危惧して投与を見合わせるかは議論の余地がある所でしょう。
予防ワクチン投与は、副作用の可能性を真剣に考え、自分で判断出来る年齢になって、適否を選択するというのが妥当な考えになりそうですが。
日本のがん生存率は高い
1995年-2009年までの67ヶ国、2,500万人のがん患者を対象に10種類のがんの5年生存率を調べたデータが出ました(Lancet 2014年)。
このデータは国際共同研究(CONCORD-2)によるものです。
この調査から見るといろいろな事が分かってきます。
1.胃がん5年生存率は
アメリカ(29.1%)、イギリス(18.5%)、ドイツ(31.6%)などに比べ、日本(54.0%)や韓国(54.0%)が高かった。
2.肝臓がんは
日本、台湾、韓国などの東アジア地区の生存率が高く20%台であったのに対し、北欧の国々では10%以下だった。
3.肺がんは
他の国の5年生存率が10-20%台、イギリスは10%未満なのに対し日本は30%だった。
4.結腸がんは
60%の生存率
5.乳がんは
生存率が各国とも高く、先進国は概ね80%超、日本も84.7%だった。
6.子宮頸がんは
日本66.3%の生存率、東アジアはほぼ同じだった。
7.卵巣がんは
日本が37.3%、アメリカ、韓国、ヨーロッパでは40%超であった。
8.前立腺がんは
各国とも5年生存率が大幅に上昇したそうです。日本では1995年-1999年の間までの例に比べると、生存率が65.7%から86.8%に改善したとの事。
9.白血病
白血病は、日本、韓国、台湾などの東アジアの国々で生存率が20%前後なのに対し、先進国では50-60%台の所が多かったそうです。
10.小児の急性リンパ球性白血病(ALL)は
オーストリア、ベルギー、ドイツなどの90%以上の生存率だったのに対し、日本は81.1%だったとの事でした。
がんに対しては地域によって差が出てくる事から、民族的な問題や遺伝的な要素も関ってくる可能性があるとの考えがあるとの事でした。
健康寿命から分かること-日本は高い-
健康寿命とは要介護など、人の手をかりずに生活できている期間を言います。
先日厚生労働省から平成22年度の健康寿命が発表されたため、記憶されている方も多いと思います。
それによると、健康寿命は男性が70.42歳、女性が73.62歳でした。
平均寿命は男性79.55歳ですから、健康寿命をこえて約9年で寿命を迎えるという事になります。
女性の平均寿命は86.30歳ですから、女性は12年半位の差があるという事になります。
さてEu諸国のデータと比較すると興味深い結果が出ています。
2009年度のEuの平均健康寿命は男性で61.3歳、女性で62歳だったそうです。
何と日本人に比べて、約10年短いという結果です。
直接比較できる2010年度でみてみると、
フランスは男性61.9歳・女性63.5歳
ドイツでは男性57.9歳・女性58.6歳
イギリスでは男性65.1歳・女性66歳(2009年度)
イタリアでは男性63.4歳・女性62.5歳(2009年度)
ブルガリアでは男性63.0歳・女性67.2歳
スウェーデンでは男性71.7歳・女性71.0歳 等
との事です。
Eu諸国に比べて、日本の健康寿命が高いのは際立っています。
日本人の食事、習慣、生活環境など誇っても良い事なのでしょう。何せ、ドイツ、フランスに比べると、男女とも10年は健康寿命が長い訳です。この点はその理由を十分に調べてみる価値はありそうです。
一方スウェーデンの健康寿命の高いのが目立ちます。これは何となく分かるような気がします。
ブルガリアが高いのはヨーグルトのせい?何しろヨーグルトを食べる人は「がん」が少ないという研究もある程ですから。
地域や国によって健康寿命に差があるのはとても興味がある事です。
振り返れば、私達の健康維持に貢献する事が見つかるかも知れません。
ピルとがん
ピルの効果や副作用が問題になっています。ここではピルとがんの関係について
■ピルによって増えると考えられているがん
1乳がん
・乳がんの発生率に差はないというデータがある一方で、やはりピルを長くつづけると、乳がんの発生の確率が高くなるという調査が多くあります。
・家族に乳がんの人がいる方は、医師と相談し、定期的ながん検診をうける事が必要でしょう。
・良性の病気でも乳腺にしこりがある時などはピルの使用を控えるよう指導をうける事があります。
2.子宮頚がん
・長く使用すると発生率が上がるという研究があります。
・少なくとも定期的に子宮頚がんの検診をうける事が必要になります。
■ピルによって減ると考えられるがん
1.卵巣がん
2.子宮体がん
3.大腸がん
ピルを用いると、何故これらのがんが減るのかは分かっていません。
減っているという根拠は、疫学的研究と言って全体の傾向をみると、そういう方向になっているという調査からです。
■ピルと卵巣がん
ピルが抑えると言われているがんのうち、今回は卵巣がんについて。
ピルが卵巣がんの発生と抑えるという事は、先程の疫学的調査で明らかにされました。
しかもその効果はピルを止めてもつづくそうです。
例えば、ピルを中止して10年未満だと約30%発生率が減るそうです。0になる訳ではありません。
またピルを止めてもその後30年間は、卵巣がん発生の比率を減らす事が可能とのデータがあります。
ただこれだけでピルをすすめる理由にはならないでしょう。
ピルの副作用として前に掲げた乳がんや、子宮頚がんの確率を上げる他、狭心症や心筋梗塞を起こす比率が高くなる可能性があります。また静脈血栓症にも注意しなければならない等、使用にあたっての注意事項が幾つか指摘されています。
心血管系の病気の予知 55歳で…
最近の報道で、お酒に弱い人は心臓疾患になる率が高くなるというものがありました。iPS細胞を使った実験との事です。
さて疫学的研究というのがあります。
環境や生活習慣等で病気に影響するものがないかなどを調べる学問です。
最近のデータでは55歳の時のいろいろな検査結果を総合すると、その人の将来の心血管系の病気になるリスクを推定出来るという調査結果が発表されました。(世界で最も読まれる医学雑誌の1つNew England J.Med.2012、に出ていた論文です。)
研究者は25万7,384人を含んだ幾つかの研究データを解析したそうですが、①総コレステロール、②血圧、③喫煙の習慣、④糖尿病の有無を検討対象にしたそうです。
その結果、55歳の時に、①総コレステロール180㎎/?未満、②血圧120/80未満、③非喫煙、④糖尿病なしの人が心血管系の病気で死亡する率が低かったそうです。
例えば、80歳までの心血管系の病気で死亡するリスクでは、55歳時点で問題がなかった人に比べて危険因子が2つ以上有った人に比べて、男性4.7%対29.6%、女性6.4%対20.5%と明らかに危険因子がなかった人の方が死亡率が低かったそうです。
日本人の平均寿命や健康寿命(人の助けを借りず自立して生活出来る人)が先進欧米国に比べて高いのは、若い頃の食生活(和食中心)、健康診断の発達など幾つもの要因が考えられます。
これからも健康な生活が出来る環境が維持されると良いですね。
携帯電話のもう1つの欠点
携帯電話は今の社会では使うのが当たり前です。持っていなければ、携帯に慣れていないお年寄りか、変り者扱いにされかねない時代です。
さらに最近は、小さい子供の位置情報を知るのにも使われ、犯罪予防の効果も期待されています。
しかし一方で、携帯電話の欠点、注意点が指摘されています。
携帯依存とも言うべき状態が1つです。
しかし、今もしかしてさらに重大な課題が持ち上がるかも知れません。
今年6月(2014年6月)には、フランスでイヤホンのない携帯電話は14歳未満の小児に売る事を宣伝してはいけないと言う法律が議会を通ったようです。
携帯電話を使い続けると脳腫瘍になる確率が高くなるからというのが、その理由だそうです。
携帯電話を成人で20年、小児で10年つづけると携帯電話を直接脳の近くで当る事で、脳腫瘍が出来る確率が高くなるとのデータがあるとの事で、使わない人の1.5-2倍になるとか。自分の意志で使わないと決める事の出来ない14歳以下の小児は「気をつけて下さい」という意味だと考えられます。
なおフランスでは、妊婦さんは携帯電話をお腹から離して持参するよう警告しています。徹底していますね。
そう言えば、携帯電話の開発、普及に尽力した有名人の何人かは、確かに癌で亡くなっている人がいます。しかも若い年で。
よく知られている世界保健機構(WHO)も携帯電話を含む電磁波を出す物質を、発がん性のある可能性があるとして(possibly)、注意を喚起しています。
たぶん電磁波を沢山浴びても何でもない人がいる一方で、影響を受け易い人もいるという事ではないでしょうか。
将来こうしたタイプの人-がんの発生し易い人-は注意が必要といった調査が出てくる様な気がします。
親子で本を音読することがすすめられています
米国小児学会(AAP)は、小児科医が小児の診断にあたる時に、診療業務として子供の読む能力、書く能力を上昇させるように努力すると良いと述べています(Pediatrics 2014年6月)。
AAPの声明によると、親子での音読では、
①子供が多くの言葉に触れる事が出来る。
②就学前までに必要な読み書き能力が得られる。
③さらにこの音読は子供の発達に欠かせない脳の発達にも良い影響を与える。
④親子関係の強化の最も有効な手段になり得る。
⑤これにより、子供に生涯ついてまわる言葉、読み書き能力、社会性や情動能力が形成されるとされています。
一方、こうした努力をしないと、3歳までに理解できる言葉の種類が少なくなるという指摘もあります。
またこの読み書き能力は、意識して手間をかけて子供に教えなければならず、家庭の所得も関連するとの話もあるとの事です。
「5つのR」について
さらにAAPは小児科医に次のような事を就学前の準備に「5つのR」として啓発するよう推奨しています。
Reading: 日常生活で本を読む
Rhyming: 韻を踏む
Routines: 規則正しい生活
Rewards: 日々できた事をほめる
Relationships: 健全な発達の基礎となる親子関係
これら「5つのR」について、子供の成長のために小児科医が保護者に伝える事が大切と述べています。
もちろん小児科の医師から伝えられるだけでなく、私達も良い事、出来る事は積極的に取り入れたいものです。
乳がんになり易い遺伝子異常をもった女性は…
将来乳がんになる可能性があるという事で、若いアメリカ女優ががんでない乳房を切除し有名になりました。
実際はその前から、手術をうけていた女性は、日本でも欧米でも多かった様です。
しかし、一方で異常もないのに両方の乳房を取るのは理解し難いという話もあります。
手術と決心した女性は、特別な遺伝子BRCA1.2を持っている人で、将来乳がんや卵巣がんになる可能性が高くなる事が分かっていました。
手術をうける事については、肯定的な意見が多いようですが、これは当事者になってみなければ理解出来ない問題です。冷静な判断が要求されるでしょう。
さてこの問題について、極めて興味のあるデータが出されました(Metcalt k らBMJ 2014)。
このBRCA 1/2遺伝子を持った女性が乳がんになった時の対応です。
BRCA1/2遺伝子陽性の女性で一方の乳房にだけがんがあった場合、①がんがあった方の乳房だけを切除した人と②両側の乳房を切除した人の将来を見たものです。
対象の女性は390人、一側だけ(がんがあった乳房だけ)切除した人が209人、両側の乳房を切除した人が181人でした。最長追跡期間20年。
平均14.3年追跡したそうですが、79人の女性が乳がんで亡くなったそうです。
その内訳は①片側乳房切除の女性が61人、②両側乳房切除の人が18人との事でした。
このデータを正しいとすると、BRCA1/2遺伝子変異陽性の女性がもし、乳がんになった場合、両方の乳房を切除した方が良いだろうという事になりそうです。
実際年令を含めいろいろ統計的な処理を加えて、冷静に判断すると、両側乳房切除により乳がんによる死亡は48%減少する事が分かったそうです。
昼寝は必ずしも身体に良くない?!
ヨーロッパ、特にラテン系の人にはシエスタと言って昼寝の習慣があるようです。
仕事をしていても、昼休みをとって必ず昼寝をする人が意外と多いとか。
私達も昼寝と言うと、身体に良いイメージがありますが、「そうとも言えない」という調査が出てきました(有名な疫学-病気に一定の傾向があるか、原因は何か等をさぐる大切な医学分野-の研究誌 Am.J.Epidemiology 2014)。
これによると1998-2000年の間でヨーロッパの人1万6,374人を13年間かけて調査した所、次のような結果が出たようです。
1日の昼寝が平均1時間未満の人は、死亡リスクが14%高くなった。
昼寝時間が1時間以上になると、死亡リスクが32%高くなったという事です。
確かに昼寝が良いと言っても、あまり長時間はもともとすすめられていませんでした。もしこの調査が正しいとすると、やはり長い時間の昼寝は避けた方が良いと言えるでしょう。
なおこの研究で分かった事は、65歳以下で呼吸器の病気がある人は、昼寝をする事で死亡率はさらに高くなるとの事です。
これに該当する人は、1時間以上昼寝をすると、昼寝をしない人に比べ約2.5倍死亡率が高くなったそうです。
このデータが本当なのか、もし本当であれば何故そうなるのか、短い時間なら身体に良くはないか等、されなる詳しい調査結果が待たれるところです。
卵巣チョコレートのう腫手術後に、ピルを使用すると再発率が下がる
卵巣チョコレートのう腫は若い人から年配の女性まで多くの人がかかる病気です。
治療法には幾つかの選択があり、年令や大きさ、症状の強さの程度などにより、治療法が提示されます。
卵巣チョコレートのう腫は、少しずつ大きくなる可能性があり、その事が将来幾つかの問題点をひき起す可能性があります。
1.痛みなどの自覚的な症状が悪くなる。
2.不妊症の原因になる事がある。
3.悪性化する可能性がある等です。
さてこのチョコレートのう腫の治療法の1つに手術による切除があります。
最近は腹腔鏡下で行われる事が多くなりましたが、手術をするので治療を終るのではなく、手術後にピルを予防的に用いると再発率が減るという研究があります。
腹腔鏡下で卵巣チョコレートのう腫を摘出し、その後ピルを使いつづけると、
3年後にはピル使用しつづけた人の再発率が 6%
3年後にはピルを使用しなかった人の再発率が 49%
という結果だそうです。明らかに手術後ピルを使用した方が、再発率が低かったそうです。
しかしこれはピルを使用できる年令の人に限ります。また赤ちゃんを希望している人には使えない方法です。
ただ赤ちゃんを希望している人は、この手術だけで妊娠率が上昇するとされています。
また年令的にピルを使用しない方が良い人は、ピル以外の薬剤を使ってみる選択はありそうです。
虫歯が多いと、がんになりにくい…とか。原因は乳酸菌?
虫歯が多い人は、少ない人に比べて、口やのどに出来る扁平上皮がん(これを頭頸部がんといいます)になるリスクが7割も低かったというデータが発表されました(M.Tegal博士ら. JAMA 2013)。
これまでは、虫歯の原因になる細菌に、がんを予防する能力があるのではないかという研究はあったそうです(細菌から出る免疫の力による)。
今回のデータが1999-2007年の8年間に博士らのがん研究所に来た頭頸部扁平上皮がんの患者さん399人を対象にした調査です。
がんの内訳は口腔扁平上皮がん146人、中咽頭扁平上皮がん151人、喉頭上皮がん102人だったとの事。
これらの患者さんと、何も異常のなかった人を比べると、虫歯の数が多い人、歯の欠けた所にかぶせる補綴物(これをクラウンといいます)の数の多い人、歯内療法をうけた事の多い人ほど、頭頸部扁平上皮がんの発生率が低かったそうです。
博士らは、こう言っています。
虫歯は歯のプラークと関係するが、プラーク内で菌が作った乳酸菌は一方で虫歯を作るものの、他方この菌が人間の炎症性の病気や、がんの予防になっているのではないかと。
もしこれが本当なら、虫歯の原因になるプラークは、長い人類の進行の歴史の中で、がんや炎症などの有害な出来事から身を守る手段となっていた可能性があります。
プラークを完全に除去するのは却って良くないという考えが、将来出てくる事も考えられます。
今までの常識が変わってくるかも知れません。
HPV感染は性病ではない
子宮頸がんの原因の大部分がHPV(ヒト・パピローマ・ウィルス)感染と考えられています(少なくとも95%)。
さてこのHPV感染は性行為がその殆んどがキッカケになるため、性病と間違える人が多いようです。しかしHPV感染は性病ではありません。
確かにHPVというウィルスは大部分は性行為で感染します。一方少ない割合ですが母子感染もあります(これは良性のHPV感染)。
しかし性行為が感染の元だと言っても、性病ではありません。
その理由は次の通りです。
もともと男性も女性も一生に一回はこのHPVに感染すると考えられています。
感染する率は全女性の80%
。
ほぼ全女性が感染する可能性がある病気は性病とは言いません。
これが理由の1つです。もう1つの理由は、HPV感染は自然に治る事が普通だという事です。性病は治療しなければ治りません。治療しなくても殆ど治る病気は性病に入りません。
ウィルスは人間に寄生しないと生きていけません。自分の子孫を残すには、人間が子孫を残す手段を利用しようと考えます。
つまり人間が子孫を残すために、性行為をするのだから、それに合わせてウィルスも次の世代に生き残りをかけようとするのです。
一生の間性行為のない人間は少数派で、性行為をする人が大部分です。つまり大部分の人がHPV感染の機会があるという事になります。
なお子宮頚がんになってしまうのは、単にウィルスが消えにくかったというだけに過ぎないと考えられています。
さて、それでは人間に感染したらウィルスはどの位生き残るのでしょう。
研究によれば、ウィルス感染後約90%の人でウィルスが消えるそうです。
この消える時期は今の所ウィルス感染から2週間から2年と考えられています。
さて、ウィルス感染後、子宮頚がんの出来やすい子宮の出口で、ウィルス感染の影響が出る時があります(何も起こらない時もあるようですが)。
影響が出る時は軽い方から軽度異形成上皮、中等度異形性上皮、高度異形成上皮、初期の子宮がんと進みます。
最も軽い異常が軽度異形性成上皮、これは今がんではないものの、軽度の異常があり気をつけて下さい。→定期的な検診をうけて下さいという事を意味します。
ここからかなり気をつけて下さいという状態(中等度~高度異形成上皮といいます)になる人は、10%前後いるそうです。
この状態から初期の子宮頚がんになる確率が大体20%という調査結果が出ています。
まとめると最も軽い異常、軽度異形成上皮になった人が、子宮頚がんになる確率が2~3%、高度異形成上皮の人が、子宮頚がんになる確率が20%という事です。
こうしてみるとHPV感染=子宮頚がんではない事が分かります。
HPV感染がある事が分かっても冷静に考える事が大切です。
わさびに抗腫瘍効果が?!
わさびの成分に抗腫瘍効果があるとの調査結果が出ていました(第40回日本免疫学会)
首都大学東京の福家洋子教授の研究グループから出たデータです。
福家教授らのグループは、わさびの中の6-MITCという物質について注目し、その抗腫瘍効果をみたそうです。
このデータは今のところ、試験管の中のデータで、今後人間に効果があるかは先の話になりますが、興味深い研究である事は確かです。
実験では人間の皮膚がんである悪性黒色腫と乳がん細胞を用いたそうです。
これらの腫瘍をマウスに移植し、「わさび」の成分の入った食べ物を食べさせた所、腫瘍を攻撃するナチュラルキラー細胞(NK細胞)の活動が増し、ヒト樹状細胞の腫瘍攻撃物質(サイトカイン)が増えたそうです。
樹状細胞というのは、最近腫瘍細胞を攻撃するという事で注目を集めている細胞です。
この作用は、予め実験動物であるマウスに食べさせていても効果があったそうです。
この実験データがさらに実を結ぶ事が期待されます。
もともと日本人は欧米人に比べ、皮膚がんの人が少ないとされています。
もしかして「わさび」が、この事に貢献しているかも知れません。
また日本人が好むものに緑茶があります。以前から緑茶にも抗腫瘍効果がある事が知られてきました。長い時間かけて育まれてきた日本人の食生活は、深い意味がありそうです。
がんは、食生活や風習の異なる地域や国で発生率に差がある事が指摘されています。
その地域の食習慣が、1つのポイントになる可能性は十分あると考えられます。
若い女性の子宮頸がんが増えている。
世界中では、増えている「がん」と減っている「がん」とがあります。
肺がんは増えていますが、胃がんは減っています。女性では子宮体がんや卵巣がんは増えていますが、子宮頸がんは減っています。
その傾向は日本でも変わっていません。
子宮頸がん患者さんは少しずつ減ってきていますが、それでも1年間に約15,000人が子宮頸がんと診断されています。
そのうち初期のがんの方が5,000人、進行したがんの方が約10,000人と言われています。
さて世界中で減りつつある子宮頸がんですが、減ってきた理由の第一に考えられているのは検診の効果です。
子宮頸がんは、検診の効果が確認されている数少ない「がん」の1つとされています。
しかし一方で憂慮されるべき問題があります。
日本では若い女性の子宮頸がんが増えている事です。
ヨーロッパやアメリカでは20-30代の若い女性の子宮頸がんの罹患率(子宮頸がんになった人)や死亡率が減っています。
しかし日本では若い女性の子宮頸がんが猛烈な勢いで増えています。
国立がんセンターのデータによれば、1990-1999年頃までは罹患率が人口10万人当り、約20人位で一定でした。
それが2000年から2005年位までは一転増加傾向になり、人口10万人当り30人に、その後はさらに急速に増加し、2008年には、人口10万人当り約60人となっています。
1990年代に比べ約3倍です。
これに伴い若い女性に限っては、子宮頸がんの死亡率が上がっています。
こんな傾向は日本だけです。
今考えられる理由は、
①性行為の年齢が若くなっている
②日本では子宮頸がん検診をうける人が少ない(欧米では若い女性の70%が「がん」検診をうけているのに、日本は約20%と圧倒的に少ない)
③欧米では、子宮頸がん予防ワクチンの効果が表われ始めている
などです。
子宮頸がん予防ワクチンについては議論がある所ですから、その使用の可否についての判定は将来に待つ事としましょう。
しかし、子宮頸がん検診は何の副作用もありません。一方で検診を受ける事のメリットは計り知れません。
産婦人科医として検査をうける事をお勧めします。
1.原因はウイルスである。
2.この20数年で、若い女性には3倍に広がっている(ウイルスが広がっている)。
3.しかし検診を受けさえすれば、心配はいらなくなる。
痛み止めはまずアスピリンを!副作用を考えると…。
生理痛や頭痛、女性にとって鎮痛剤は必須品と言えます。
幸い鎮痛剤の種類は多く、現在は手軽に手に入れる事が出来ます。
さて、鎮痛剤を選択する時、皆さんはどうされていますか。
テレビのコマーシャルを参考にした人、親や友人からすすめられた人、昔から同じ薬を使っている人など、鎮痛剤の選択の基準は様々でしょう。
しかし、薬を使うからには(それも長く使う)、薬そのものについての正しい情報を持つ事が必要です。
薬については、いろいろな調査データがあります。
これらの情報は、まず医師の間で読まれる専門誌に提出されます。
当欄でもかつてお伝えした事があります。広い範囲で使われている薬でも、実は注意した方が良いとの研究結果が出ているものがあります。
例えばボルタレン等の鎮痛剤には、大量にしかも長く使うと泌尿器系の臓器に障害を起す可能性があるという調査があります。
ロキソニンを長期間継続して用いると、将来腎がんになる可能性が高くなるというデータ(約3倍)も出ていました。腎がんは増えてきているがんの1つです。
一方、昔から使われているアスピリン(バファリン)については好意的なデータが多いようです。
使い方にもよりますが、アスピリンは大腸がんや食道がんを予防する効果があり、さらには大腸がんになった人の転移を防ぐというデータが出ています。
腺がんというタイプのがんに良いようです。
最近でも欧米の白人に多いメラノーマ(悪性黒色素)という皮膚のがんの予防になるという調査結果が出ていました(Cancer 2013 -- 世界で最も権威のあるがんの専門誌です)。
これは、単に日常の鎮痛剤として、アスピリンを採用するだけで、将来のメラノーマの発生を抑えるというものでした。
この他アスピリンには、血管の病気(脳や臓の血管を含む)の発生を抑える作用がある可能性が指摘されており、女性に心強い薬剤と言えます。
こうなると痛み止めの第一選択はアスピリン(バファリン)になると考えて良さそうです。
今の所なぜアスピリンが「がん」や血管の病気に良いのかは、はっきりしておりませんがアスピリン(バファリン)の炎症を抑える作用が良いとの考えが有力なようです。
ただアスピリンは全く害がない訳ではありません。例えば胃腸障害(胃炎や胃潰瘍など)が起る事はありますし、将来思いがけない副作用が指摘される事があるかも知れません。
こう考えると、日頃使っているお薬については、常にアンテナを張っておく事が大切だという事になります。
鎮痛剤はとても強い味方です。しかし、一方で手軽に使うのは考えものです。必要な時に、必要な量だけ使うのが大切だろうと思われます。
最近 子宮体がんが増えています。
子宮がんには「子宮頚がん」と「子宮体がん」があります。
2つとも子宮がんですが、実は全く別のがんです。
これらのがんは①出来る場所、②出来やすい年令、③原因等が全て異なります。
子宮頚がんは、HPVというウィルス感染が原因で年令も20代から注意が必要です。
このがんは検診で、早期の段階で発見されます。またHPV予防ワクチンが使われる様になり少しずつ減ってきています。
これに対し子宮体がんは50歳代をピークとして、だんだん増えてきています。
少し前までは子宮頚がんと子宮体がんの割合は6:4で子宮頚がんの方が多かったのですが、ごく最近のデータでこの比率が5:5となっています。
今回は最近増加が目立つ子宮体がんについて少しお話をしましょう。
子宮体がんは50代に最も多く見つかり、次は60代と言われていましたが、最近若い女性でも見つかるようになってきました。
このがんは子宮の奥深くに出来ますが、分厚い子宮筋肉の中を進みますから、その分進行に時間がかかる事が多く、早目に発見されれば完全に治る事が見込めます。
早期の診断が必要な代表的な女性のがんと言えるでしょう。
早期に発見のコツは
① 40代を過ぎたら子宮頚がんと一緒に検査をうけてみる事です。
② 不正出血が最初の症状が多いと考えられています。このため45才を過ぎて出血のある人は検査をうける事が必要です。
③ 肥満の人は子宮体がんになるリスクが高いと考えられています。
最近のデータでは、病的肥満がある女性では、肥満のない人に比べると3.4倍子宮体がんになる確率が高かったそうです。(OB-GY 2012)
ただし、ここでの病的肥満とはあくまで「病的という事」で、少し肥っている位の人は対象ではありません。
④ もともと月経不順があった人も注意が必要です。多のう胞性卵巣(PCO)で治療をうけた事のある方は、注意をした方が良いとの考えがあります。
⑤ 結腸-大腸がんになった事のある人も子宮体がんに気をつけるべきとの事です。がんになる危険率が約4.4倍になるそうです。
⑥ 子宮内膜にポリープのある人は、子宮体がんになるリスクが高いというデータがあります。子宮内膜ポリープがない人に比べると、子宮体がんになる可能性が約4.1倍だったそうです。(OB-GY 2012)。
⑦ 何らかの機会で婦人科臓器を超音波で調べた時に、子宮内膜が厚い人は検査をうけた方が良いと考えられています。また子宮が大きい人も調べておいた方が無難です。
⑧ 病的な肥満、子宮内膜ポリープ、結腸-直腸癌になった事がある等をリスク因子といいますが、これらのリスク因子を2つ以上もっていると、生涯子宮体がんになるリスクは32%との事です。つまり2つのリスクを持っている人の1/3は、子宮体がんになる可能性があるという事になります。
極度な肥満はコントロール出来るもの。
小太りの女性の方が長生きし、認知症になりにくいというデータがありますが、やはり極端は良くないようです。
妊娠早期の血液検査で胎児の性別が分る。
女性は、妊娠すると最も気にする事は赤ちゃんの健康です。
次に気になるのは多分性別だと思います。
産科の医師は、赤ちゃんがある程度大きくなると決まって、うちの子は「男の子ですか」あるいは「女の子ですか」と尋ねられます。
これまで性別は、例外的な場合を除いて、ある程度胎児(赤ちゃん)が大きくなってからでなければ分かりませんでした。
またよく間違う事もあって、産科医の中には、半分冗談で「もし間違えても私を怒らないでね」という人もいる程です。
しかし性別の判定は、時に重要な問題を含む事があります。
特別な病気ですが、性と関連する病気、例えば男の子にだけ症状が出てくる病気などがあります。これを伴性遺伝性の病気といいます。こうした素因をもっている女性にとって、性別の判定はとても大切な問題になります。
さて、この性別の判定を、妊娠の早い時期から正確に行おうという研究があります。
この研究はもう既に実を結び、イギリス、オランダ、フランスなどのヨーロッパ諸国の中では妊娠中の普通の検査の中に組み込まれています。
さらに男女の判定器具は、インターネットでも販売されています。これらの器具は妊娠の5週から7週の早い時期から判定が可能とのふれ込みだそうですが、それについての研究のデータが出ている程です(JAMA 2011)。
これはお母さんの血液の中を流れている、赤ちゃん由来の遺伝子を調べるものですが、検査の精度は高いと考えられています(的中率95-99%程度)。但し精度は妊娠の早期よりも妊娠が進む程高くなるそうです。また尿から検査する方法もありますが、尿による検査より血液による検査の方が精度が高いとの事です。
そんな事知らなかった?! 小麦粉の中に…。
日本の小麦粉の輸入量は、日本全体の使用量の約90%だそうです(2010年)。
何げなく食べている食品の殆どが輸入品という事になりますが、実はかなりの国で小麦粉中に葉酸を入れているそうです。栄養強化が目的だとか。
この小麦の輸入先は、アメリカが58%、カナダが21%、オーストラリアが20%(2011年)との事ですが、これらの国々では全て小麦粉に葉酸を添加する事を義務付けているそうです。
栄養強化が目的の他、アメリカやカナダでは、赤ちゃんの先天的な病気(脊椎二分症や、神経管の病気)の予防になるからという考えがあります。
しかし、2007年イギリスの食品基準庁から、これは正しいのかという疑問が出された事があります。
さて、2013年Lancetという医学雑誌に、葉酸のサプリメントが安全かというデータが出ていました。
調査の対象は、葉酸サプリメントを服用して、大腸がん、前立腺がん、肺がん、乳がんなどの個々のがんの発生率が高くならないかというものです。
その結果、5年間の短期間であれば、こうした葉酸のサプリメントが、がんの発症を増加させる事は無いとの結論でした。
またこの研究では、小麦粉に添加されている葉酸は、サプリメントで摂られる葉酸に比べると、はるかに少ない量だと述べています。従って、葉酸添加を義務付けている国にとってはこの結果は安心だろうとしております。
しかしそうとは言っても、一生食べ続ける食品の中に人工的に加えられた成分があるとしたら、少し気になります。量は少なくても、長く食べ続けていて何か起る可能性だってあるかも知れません。
前に述べたイギリスの「食品基準庁」は、2007年の時点で、閉経後の乳がんの発症率が高まるのではないかとの疑問を出しています。
私は輸入小麦に葉酸が加わっているなんて知りませんでした。
葉酸がそんなに大切なら、別に葉物を食べれば良いだけという気もしますが…。
日本に輸出する分だけ葉酸を添加しないという訳にはいかないでしょうから、心配な人は国産品を使えという事になるのでしょう。
赤ちゃんにコレステロールが大切!
お腹の中の赤ちゃん(胎児といいます)には、ある程度のコレステロールが必要な事が知られています。
コレステロールは血管の壁の働きに関係したり、大切なホルモンの原料になったりします。さらに胎児の発育に関係している事も分かっており、コレステロールの異常によっては胎児の奇形の原因になるという調査もあるそうです。
もともと胎児はコレステロールを自分で作る能力が低いと考えられています。
このため妊娠の初期では特にお母さんからの供給が大切になります。
最近、お母さんのお腹にいる胎児のコレステロール産生能力を測定した研究の結果が出ていました(M.B.Baardman ら、AJOG 2012)
これはお母さんの羊水を調べたデータですが、それによると、
1.胎児は妊娠19週までは、コレステロールを自分で作る能力は低いのではないかという事だそうです。
2.一方で、お母さんから胎児へはコレステロールが移送されていると推定されました。
3.また全てのコレステロール(胎児が作る分も、お母さんから来る分も)が、妊娠15週から22週にかけては僅かに上昇している事も推測されました。
コレステロールの大切な作用は沢山あります。
例えばコレステロールが少な過ぎると、コレステロールを原料とするステロイドホルモンが十分に作られない可能性があります。もしそうであれば赤ちゃんが生まれる時、ストレスに十分に対応出来ない事も考えられます。
そして何よりコレステロールの量が適切でなくて、赤ちゃんの奇形の原因になっても困ります。
今の所、何をどのようにと言った細かな基準はありませんが、お母さんのしっかりした栄養管理が大切だという事は言えそうです。
赤ちゃんは体内の記憶がある
最近小さな子供の胎内記憶(お母さんのお腹の中にいる時の記憶)が話題になっています。小さな子供達からアンケートをとると、いろいろ興味ある結果が出てきます。
その中でも最近特に話題になっているのは、お母さんのお腹の中にいた時の記憶です。
「お水の中をプカプカ浮いていた」
「あたたかかった」
「うす暗かった」
「外がほんのり明るかった」
「急にガヤガヤすると思ったら、周りに沢山の人がいた-お産の時らしい」
「お母さんの声が聞こえていた」
「お母さんの声が急に変った」
等々さまざまなメッセージがある様です。
普通お母さんのお腹の中でのこうした記憶は、どの赤ちゃんにもあるのだそうですが、出産の時の環境の急激な変化とともに、忘れる事が多いのだとう事です。
しかし、中ではそのまま記憶が残っているお子さんもいるらしい事が分かっています。
皆さんのお子さんはいかがでしょうか。
なお記憶の中では、お母さんの安定した声に安心したというものが多いようです。
リラックスした環境があるのは良いものなのですね。
血液検査で自分の寿命が分る
糖尿病の診断や経過をみるのに役割の検査の1つにHbA1cというのがあります(ヘモグロビン、エー・ワン・シィー)。
このHbA1cとは、血管の中にあるヘモグロビンという蛋白質に糖が結合したものを言います。
この値は血液中の糖分の濃度と関連する事から最初に述べたように、糖尿病の診断や経過観察の指標として使われています。
例えば、HbA1cが高いと(6.5%以上)糖尿病の疑いとされます。
さて動脈硬化の研究をしていたグループが、HbA1cの値と将来の死亡との関連を調べた興味深いデータが出ました(Aggarwal V.ら Diabtes Care 2012,35:2055-2060)。
ここではHbA1cの値が高い人ではなく、低い人に注目したようです。
これによると、HbA1cの値が低いグループの人(5.0%未満の人)は、高コレステロールの少ない人が多かったものの、全死亡(原因を問わず死亡した人)と、がんによる死亡のリスクが高かったそうです。
全死亡の率は 1.32倍
がんによる死亡の率は 1.47倍、
であり統計学で言うと確かだろうと述べています。
この他統計学的に差があると断定出来ないものの、心臓血管による死亡と、呼吸器の病気による死亡の割合も高くなる傾向があったそうです。
こうして見ると、身近な検査で自分の将来を予測する時代が来るかも知れませんね。
サプリを飲むより良いこと-その2-
サプリメント(サプリ)が本当に役に立つのかは科学的に証明されたとは言い切れません。
好意的にとっても、飲んでも飲まなくても同じという程度になるでしょう。
現在の所、科学的に証明されている身体に良い行動にサプリの摂取は入っていません。
今良いと考えられているのは、例えば
①運動すること。
・がんの予防や進行を抑えるという説があります。
・少しうっすらと汗をかく程度の運動を1日20分位は行う。
・しかもこの運動は貯金出来るらしい(例えば1時間行うと-3日分になる)。
②野菜や果物を1日5種類以上は摂る事
特に白い果物(リンゴ、ナシ等)を十分に食べる人は、食べない人に比べると脳卒中になる確率が5割も減るというデータがあります。
③太り過ぎない事
一方で小太り程度だと長生き、認知症になりにくいというデータもあります。
④適量のお酒
・地中海食などで知られているように、適量のワインなら身体に良いというデータがあります。
・日本酒も同様で1日1合(多くて2合)位なら良いとの考えがあります。
・但し、もともとアルコールが苦手な人が無理に飲む必要はありません。
⑤タバコは利点がありません。
・子宮内膜症の進行を抑えるという研究がありますが、全ての婦人科医が認めている訳ではありません。
・タバコの習慣は麻薬と同じというデータがあります。
これらを考えると、サプリより良い事はたくさんあるようです。
サプリを飲むより良いこと-その1-
最近サプリやそれに似た商品の宣伝が目につきます。
サプリを摂るか摂らないかは自分で決める事でしょうが、産婦人科医が尋ねられるのは、妊娠している時。
女性は妊娠すると、まずお腹の赤ちゃんが心配になります。
妊娠中は殆どのサプリはペケです。
多分飲んでも何の役に立たないか、赤ちゃんに害があるかです。
例外なのは、葉酸(純粋の葉酸だけです-他の成分が入っているものは不可)だけ、他はせいぜいカルシウムと鉄分のみ。
しかしこれらも、普通の食事に少し気をつければ良い食品ばかりです。
赤ちゃんが出来た時、赤ちゃんの為に何か良い事をしてあげたいと思うのは当然ですが、考えるとしたら、余計なものを摂らないという心掛けだと思います。
実際には赤ちゃんにはすすめられないと分かっている成分(例えばビタミンEやAなど)、赤ちゃんにどんな影響があるか分かっていないもの等いろいろあります。
お酒は妊娠中は飲まないでくださいとの標示があります。
お酒については、作る方も売る方も社会的責任があるとい訳でしょう。
医療施設や薬局で出る薬については、妊娠中に飲んではいけない薬、飲む時に厳重な注意が必要な薬、飲んでも良い薬など、かなり厳密なチェックがあります。
これも薬を出す側の社会的な責任があるからです。
しかしサプリにはこうした標示がないのが殆どです。
これは自分の責任でという事になります。
よく売れているようだから、テレビで宣伝しているから、などは安全の保証にはなりません。御注意を。
チョコレートの「旨い」おはなし。
世界中に和食の情報が広まって、ヘルシーな食事としての評価が高まっています。
しかし一方で世界の他の食品の利点も日本に紹介されています。地中海食もその1つです。
地中海食と言えば、豊富な魚介類、オリーブ油、そしてワインの効用等いろいろありますね。
この中でワインに含まれるポリフェノールは、血圧を下げたり、コレステロールを下げる作用があり、結果的に将来の心管系の病気(心筋梗塞や脳梗塞)の予防になるとの考えがあります。
認知機能の低下を予防する効果もあるとか。
さて、このポリフェノールが多い食品には他にチョコレートやココアがあります。
チョコレートの中には、ポリフェノールの一種のフラボノイドが豊富に含まれていますが、このフラボノイドの効用について最近いろいろな好意的なデータが出ています。
①抗酸化作用があり、がんの細胞の活動を抑える。
②血行を良くする事で、脳梗塞や、心筋梗塞を予防出来る。
③悪玉コレステロールを下げる作用がある。
④抗ウイルス作用があるらしい。
等です。
こう考えると、バレンタインは過ぎましたが、お父さんにあげる義理チョコなんかは、とても意味がありそうです。
このフラボノイドが多い事に注目してでしょうか、チョコレートの中でもカカオ成分の多いダークチョコレートの効用を調べた研究があります(ダークチョコレートとは、カカオ含量60%以上のものを言うそうです)。
メタボリック症候群の基準を満たした男性にダークチョコレートを毎日100gづつ食べてもらったところ、死に至る心臓血管系の病気になる危険性を減らす事が分かったとの事です。
しかも、これはチョコレートの量が多くなると効果が高まったとか。
薬でなく、ダークチョコレートで病気の予防になるというのは文字通り「旨い話」です。
ただし既に糖尿病の人や、その危険のある人は対象になりません。また1日100gというのは身体の大きい外国人を対象にしたものです。
このため日本人には、やや少な目の方が良いかも知れません。
ホルモン補充療法は乳がん発生を抑える事も?
ホルモン補充療法と言ってもいろいろな方法があります。
女性ホルモンのうち卵胞ホルモン(エストロゲン)単独を用いる方法、黄体ホルモン(プロゲステロン)と一緒に用いる方法(代表的なものはピル)等です。
このホルモン補充療法は以前、女性の健康について助言する世界的な組織(WHIといいます)から、長期間用いると、乳がんや脳卒中発作、あるいは血栓症などになる率が高くなるとのデータが出され、大きな影響を与えた事を前回述べました。
実際アメリカでは、WHIの調査結果が出た以後、ホルモンの処方をうけた人が大幅に減ったようです。
さてこのWHIの調査の後日があります。
ホルモン療法を行うと副作用が起る可能性がある事から、ホルモン療法を続ける試みが中止となりました。
しかし当時ホルモン療法を受けていた人が、その後どうなったかの調査が最近出ています(Lancet Onclolgy 2012)。
対象は子宮の全部を摘出した女性。
調査対象になったのは7,472人
使用されたホルモン剤は卵胞ホルモン(エストロゲン)だけです。
平均のホルモン使用期間は5.9年
ホルモン使用開始から約11.8年だったそうです。
その結果は
①ホルモン剤を使用した人は、乳がんになるリスクが 23%低下しました。
②ホルモン剤を使用した人は、乳がんで死亡するリスクが63%も低下しました。
③全ての死亡に関するリスクも38%低かったとの事です。
これらの結果をみると、卵胞ホルモン(エストロゲン)は立派な効果を上げる薬剤だという事が分かりました。
但しもちろんこれらの結果からホルモン剤(エストロゲン)を乳がん予防薬として考えてはなりません。
あくまでこれらのデータは子宮全摘した女性のものだけだからです。
子宮のある女性では、このホルモンの長期投与が子宮体がんの誘因になる可能性があります。
しかし、ホルモンにはいろいろな作用があります。今後女性にとってメリットのお話が出てくる事も十分に考えられます。
笑いの力ってすごいらしい!
日常生活に笑いがあるのは幸せな事ですね。
本人だけでなく、周囲の人々にも幸福な気持ちを与える事が出来ます。
もともと笑うという動作は人間にしか出来ない行為だそうです。
何らかの場面に遭遇し、笑うという行動に移るのには、極めて高度な脳の反応が必要だとの事です。
という事で、笑いと脳の関係が深い事も知られていますが、笑いは脳の認知機能に関連するという調査があります(大阪大学公衆衛生学 大平哲也准教授 2011)
それによれば、笑う頻度が少ない人ほど認知機能が低下したり、うつ気分になる率が高くなるそうです。
殆ど笑わない人は、ほぼ毎日笑う人に比べると、将来認知機能の低下は、ほぼ4倍になるとか。
笑う事は運動になるとのデータもあります。
また笑いとがんの関係も話題になっています。笑いには、ナチュラル・キラー細胞(がん細胞を攻撃する細胞と言われています)の活動を活発にするとの考えがあり、よく笑う事で、がんの進行を予防しようという試みがなされています。
これらを考えると、笑う事は精神的にも身体的にもとても有効な事と言えるでしょう。
ラジオの時代、流れていた落語や漫才は人々の心にやさしいメッセージを届けていた可能性があります。
瞬間芸ではなく、じっくりと笑みを浮かべる、ワッハッハッと笑う、そんな環境が広がると良いですね。
ヘルペスウイルス感染は活火山?!
外陰部に出来るヘルペスに感染すると、痛みや痒みの症状が出る他、発疹や小さな潰瘍が出来てきます。
再発が起こり易い事もよく知られています。
これらの症状は、疲れやストレス等が再発の引き金になる時もあります。
しかし再発の時は、軟骨や内服剤で比較的早くに良くなる事が多いようです。
発疹や皮膚の症状(小さな潰瘍など)も、痛みや痒みが消えるとともに消える事が殆どで、そうなると、ヘルペスウイルスの活動が一時的に止ると考えられていました。
つまり症状が出ている時は活火山。症状が出ていない時は休火山という考えです。
しかし最近新しい研究結果が注目されています。(J.Schitterら)
外陰部の感染した所からは、常に少量だけど、ウイルスが放出されているというのです。
もともとこれらの親類のウイルス(例えば帯状疱疹ウイルスなど)は神経細胞にとり付くと考えられています。
外陰部に出来たヘルペスウイルスも、ここにある神経細胞にとりついて、少しずつだけど神経細胞を通して外陰部にウイルスを放出しつづけているというものです。
一気に噴火する訳ではないものの、でも少しずつ噴煙をあげている浅間山みたいなものかも知れません。
この常に排出されているウイルスが外陰部の皮膚の細胞にとりついて、十分な量に達すると症状が出てくると言うのです。
この考えでいくと、外陰ヘルペスは、常にウイルスを放出しつづけている活火山という事になります(浅間山も時々噴火します)。
このウイルスを完全に抑え込むのには、
1.まず予防のワクチンの開発が必要とされるでしょう。
2.しかし、既に感染している人に対しては、症状が出ている時だけでなく、症状の出ていない時でも、長期間抗ウイルス剤を内服し、いつも出ているウイルスの量を少なくするか、ウイルスの力を弱めようとする治療法が効果を表わす可能性があります。
アスピリンのがんの転移予防効果
アスピリンは、食道がんや大腸がんの予防になるとの研究が数多くあります。
特にこれらのがんになった方々の将来の再発予防の効果がある事は、たびたび指摘されています。
最近、アスピリンはがんの中でも「腺がん」の予防と、がん発生後の転移を抑える作用があるとの研究結果が出ていました(Rothwll PMら、Lancett 2012)。
これは以前も研究の結果が出た事のある、アスピリンと血管の病気の関係(狭心症や心筋梗塞の予防にアスピリンがどれだけ有効か等の調査)を調べているうちに出てきた貴重なデータです。
①アスピリンを飲んでいる人は、がんになっても肺や肝臓など、発生した場所から遠い所へ転移する人(これを遠隔転移といいます)の割合が少なかった。がん(特に腺がん)によっては約50%近くも少なかったそうです。
②そもそもアスピリンを飲んでいると、診断された時に転移がないタイプであれば、将来転移するリスクも少なかったとの事です。
その結果、アスピリンを飲んでいる人は、診断した時に転移がなかった患者さんの場合、がんの死亡率が少なかったそうです。特に大腸の腺がんの人の死亡率を減らしたとの事。
大腸がんは現在日本女性のがん死亡率1位のがんです。貴重な研究と言えるでしょう。
但しアスピリンは、腺がん以外の固形のがんには効果がなかったとの事でした。
今の所アスピリンは、がん細胞が増える事、転移する事を予防するらしいと考えられていますが、もしそうであれば、何故そうなのかという事が研究されているようです。
しかし一方でアスピリンは出血傾向が出る等の副作用が出る時があります。アスピリン使用については、医師との十分な話し合いが必要なのは言うまでもありません。
必須栄養素コリンが乳がんの予防になる 卵、コーヒー、大豆…。
食べ物からでなければ摂取できない栄養素に「コリン」があります
身体の中では神経伝達物質である「アセチルコリン」や「レシチン」の構成成分です。
この「コリン」が女性のかかる癌で最も多い乳がんの発生を抑える作用があるのだそうです。
この「コリン」の適切な摂取量は女性で1日425㎎だとか(妊娠中は450㎎)。
卵1個にコリン125.5㎎入っているそうです。
この他コーヒー、大豆、レバー、カリフラワー、小麦の胚芽などに「コリン」が多い事が知られています。
このうちカリフラワーは「癌」全体の予防効果がある事が知られています。
またコーヒーは心臓血管の病気や癌の予防になるとか。適切な量の食事をバランスよく食べる事が大切なようです。
なお卵の事であと少し追加を。
身体中にあるリン脂質ホスファチジルコリン(レシチン)は血管の中をきれいにする作用があります。
このため心臓や脳の血管の老化を防ぎ、心臓の病気の予防や認知能力の低下を防ぐ作用があります。
またビタミンEも豊富。
このビタミンは老化を防ぐ事で知られています。
卵類の食べ過ぎはコレステロールの増加と関係するという事で嫌がる人も多いようですが、適切な量であれば健康に良いという事になります。
月経前症(PMS)に悩んでいる人…食事に気をつけてみては?
最近外来に月経前のイライラ感、うつ気分など、月経前症と言われる症状を訴えてくる人が増えてきている様です。
月経前症(PMS)という言葉も広く認知されている様で、予め「私はPMSだと思います」という方も珍しくはなくなりました。
今の所このPMSに対する治療の仕方に2つの流れがあります。
1つはピルを用いる方法、1つは脳内の神経伝達物質を増やす方法(安定剤の中などに含まれます)です。
ところで薬に頼らずに、何とかこのPMSを改善する方法はないでしょうか。
今の所すぐに効果を表す方法はなさそうですが、改善のカギの1つに日頃の食事というのがあるそうです。
日頃忙しくて、食事の内容が偏ったりしていないでしょうか。ついコンビニでの食品に頼っている事はありませんか。そして体重の増加がいやでダイエットに気を使う事はありませんか。
食事をしたり、人からほめられたりして嬉しいと思う気分になった時に、脳の中でグルタミン酸が活躍するというデータがあります。
ずっーと昔にはグルタミン酸に脳の働きを良くする作用があるという事で、コーヒーの中にも旨味調味料を入れる事が流行した事がありました(ほんの一時、そして一部の人達だけでしたが)。
この旨味の成分がグルタミン酸です。
最近はこのグルタミン酸が脳の感情に重大な役割を果たすのではないかという考えがあります。
PMSに対する効果も期待されています。
さてその為には、
1 コンビニ等で出来合いだけの食品に頼らない事。
2 もう1つ、1品でも2品でも自分で美味しいと思う食べ物を作ってみる事、などがすすめられ始めているとの事です。
陣痛に耐えた方が、赤ちゃんがたくましくなるという説
最近は、男性が女性にとてもやさしくなっています。奥さんが陣痛で苦しんでいると、医者や助産師に「何とかできないの」と言う人が増えてきました。
これは夫立ち合い分娩が増え、陣痛を目の当りにするとビックリする為もあるかも知れません。
大部分のお母さん方は、十分陣痛に耐えていますし、分娩後はその痛みを逆に赤ちゃんへの愛情に変える本能をもっています。
お産の体験をつづった先輩達の本には、
1 赤ちゃんが生まれた瞬間、痛みなんてふきとんだ。
2 すぐ次の赤ちゃんの事を考えた
など前向きの意見が並んでいます。
さて陣痛が強くても耐えた方が良い理由があるそうです。
10年位前の研究データに、強い陣痛に耐えたお母さんから生まれた赤ちゃんは、成人になってからストレスに強いというのがありました。
もしそれが本当なら、結果的に帝王切開になっても、ある程度陣痛を経験するという事は意義があるという事になります。
陣痛が強くてつらいお母さん、陣痛がつらいのではと心配なお母さん、そして奥さんの陣痛を前にして、悩んでいるお父さん、その陣痛は、実は赤ちゃんの為に役に立っている可能性もあるかも知れないのです。
但し陣痛は、ただ耐えて下さいというものではありません。産科医や助産師さんからこの陣痛のお蔭で赤ちゃんがどの位下がってきたか、お産がどの位進行してきたかを聞く事も大切です。
これらの事は、何よりお母さん達の励みになるでしょう。
カンジタの薬ががんにも効くかも知れない
がんに対する研究はいろいろな角度から進められています。その研究の広がりはとても一口では言い切れません。
日本の統計をみると、国民の2人に1人は一生のうちに1回は、何らかのがんに患かります。そして3人に1人はがんで亡くなっています。がんに対する研究が1日も早く、そして一歩でも進む事を祈りたいものです。
さて、がんをやっつける対策はいろいろな方面で進められています。
今回も注目すべき研究の結果が出ていました。
カンジタ症という真菌(カビの一種です)に効く薬(抗真菌剤といいます)に強い抗がん作用があるというものです。
ドイツの大学の先生の研究結果ですが、もしこれが本当なら、がんではない正常の細胞に悪い影響を与えずに(副作用が出ずに)がんに効果がありそうです。
ただ、今の所どのがんにどの程度効くか、効果のある量はどの位か、他の病院で試したら、やはり同じ程度の効果が出たか等については、まだ次の情報が出ていません。
抗真菌剤を長く用いて、もし真菌に感染した時に今度はその真菌剤が効くかの問題もあります。
しかし、とても重要な情報に違いはありません。
さらに一層の研究が待たれています。
睡眠時間と関係するがん-その2-
寝不足は乳がんになる確率が上がる?
睡眠不足は身体のいろいろな機能に影響を与えます。
免疫力等、病気に対する抵抗力を低下させる可能性もあると考えられています。
2009年日本疫学会(疫学というのは一言で言えば病気の原因をいろいろな角度から研究する学問をいいます)では、睡眠時間が少ないと、乳がんになるリスクが高まるのではないかという研究の結果が出ていました(東北大学-柿崎真沙子氏ら)。
平均睡眠時間が6時間以下の女性は、睡眠時間がそれ以上の人に比べると、1.62倍危険率が高まるというものです。
これには催眠物質であるメラトニンが関係している可能性があるそうです。
メラトニンが十分に出る(睡眠が十分にとれる)と、乳がんの発生と関係する女性ホルモンの分泌が減るという考えと、メラトニン自体ががん細胞の成長を抑えるという考えがあるようです。
これは前回お話した前立腺がんの研究とほぼ同じ傾向と言えるでしょう。
睡眠時間と関係するがん-その1-
前立腺がん、卵巣がん、子宮体がん、乳がん
睡眠時間と関係するがんがあるらしい事が分かってきました。
睡眠時間と健康にはいろいろな調査や研究があります。
その中で分かってきたのは、その人に適当な睡眠時間には個人差があるとの事です。ただ睡眠時間が極端に短いと、健康に良くないという考えが多いのは言うまでもありません。
今のところ健康に害があるのは、5時間以下とか6時間以下との説があります。
さて睡眠時間が長くなると、メラトニン分泌時間が長くなります。
このメラトニンというのは睡眠と関係する物質です。
このメラトニンの効果の1つに、十分に出ると性腺刺激ホルモン(男性や女性の性腺を刺激します)の働きを抑える作用があります。
その結果、性ホルモンが関係するがんの発生が少なくなる可能性があるという考えがあります。
女性では 乳がん、子宮体がん、卵巣がん など、
男性では 前立腺がん など。
メラトニンのもう1つの効果は、がん細胞の成長を抑える効果があるという事です。
さて、このメラトニン-睡眠時間と前立腺がんの関係を調べた研究があります。
これによると、2万人以上の人を追跡し、睡眠時間と前立腺がんの発生を調べた所、睡眠時間が9時間以上の人は、前立腺がんの発生率が低く、6時間以下の人は発生率が高くなるという結果が出たそうです。
なお睡眠時間があまり短いと免疫力が落ちるという研究もあります。睡眠時間とがんの関係については単にメラトニンだけではないかも知れません。
そう言えばナポレオンは、胃がんだったという説がありますね。
睡眠時間が3時間だったというナポレオンは、メラトニンの分泌が少なく、胃がんになり易かったのかも知れません。
妊娠中の女性にインフルエンザワクチンを投与すると、赤ちゃんにも効果が?!
我が国では妊娠中の女性にインフルエンザワクチンを投与して良いのか、まだ議論があります
しかし国によっては、妊娠中に積極的にインフルエンザワクチンを投与する所もあるようです
例えば、ドイツではワクチンの接種が公費で負担され無料です。
ドイツに限らず、妊娠中にインフルエンザワクチンを投与すべきと考えている国は幾つかあります。
その目的は勿論、インフルエンザ感染に弱い母体の保護のためです。
ところが最近、とても興味深い調査結果が出てきました。
妊娠中にインフルエンザ予防ワクチンをうけると、ワクチンを受けた母体に効果があるだけでなく、お腹の中の赤ちゃんにもインフルエンザ予防効果があるのだそうです。
もともと生まれて6ヶ月以内の赤ちゃんは、インフルエンザにかかりにくい事が分かっています。これは母乳の中に、インフルエンザを予防する成分が入っている事と、お母さんのお腹の中にいる時に、胎盤を通って、インフルエンザ感染に強い体質が伝えられているからです。
しかし、1度インフルエンザが流行すると、インフルエンザの感染率や死亡率は、出生後6ヶ月未満の赤ちゃんの方が、6ヶ月以上の赤ちゃんより高くなるとの事が知られています。
さて、妊娠中にお母さんがインフルエンザの予防注射を受けると、生まれた赤ちゃんのインフルエンザ感染率が減り、入院率も減ったとの事です(インフルエンザ流行期でも)。
また赤ちゃんの持っているインフルエンザの抵抗力(抗体価といいます)も、予防注射をうけたお母さんから生まれた子の方が髙かったそうです。
日本でも将来、妊娠中のインフルエンザ投与の効果について議論が出てくる可能性があるでしょう。
妊娠中の鉄分、葉酸の必要性
小児の知能や運動能力が上がった
世界で信頼されている医学誌 JAMA(2010年)に、妊娠中のお母さんは、葉酸と鉄分を十分にとると、出生後赤ちゃんの知能や運動能力が良くなる可能性があるという調査結果が出ていました。
今回の調査は、栄養状態のあまり良くないと考えられるネパールの農村で行われました。
妊婦さん達に、いろいろな栄養素を組み合わせて飲んでもらい、生まれた赤ちゃんにどんな影響が出たかを調べたものです。
なお選ばれた栄養素は、いずれも妊娠中に必要と考えられたものばかりで、不必要と考えられる要素は入っていなかったようです。
これらの栄養素は、サプリメントの形で、妊娠初期から産後3ヶ月迄毎日摂取してもらったそうです。
その結果、試験期間中に生まれ7-9歳になった676人の子供を調べた所、鉄と葉酸を選択して十分食べたお母さんから生まれた子供のいろいろな能力が上がったそうです。
詳しく言うと
1.小児の知能(記憶力と推論する能力)
2.物事を処理する能力
3.バランスの良い器用さ-運動能力
等が上昇したそうです。
妊娠中や出生直後は、赤ちゃんの脳の発達と特に関係する時期と考えられています。
この時期、特に鉄分は脳神経の発育に影響する可能性があるそうです。
これらの点を考えると妊娠中の葉酸と鉄分の十分な摂取は、大切と考えられそうです。
心臓の弱い男性に男性ホルモンを!
実験室レベルでのお話ですが。
男性ホルモンの1つに、テストステロンというホルモンがあります。
このホルモンは最近いろいろな話題を集めています。
例えば、このテストステロンの値を測ると、男性の寿命が分かる可能性があるなど(院長のコラム~自分の寿命が分かる時代が来たかも!~をご覧下さい)
さて今回はこのホルモンと男性の心臓の働きの話題です。
男性の心臓が悪い人に、このテストステロンを投与すると、心臓の働きが良くなるそうです。
これは、このホルモンが心臓の筋肉の合成と強化を行い、血管を拡張する能力があるためではないかと考えられています。
この研究には、女性の更年期障害の時に用いられる、女性ホルモンの入った貼付剤と同様、テストステロンが入った貼付剤を用いたそうです。
女性用のホルモンの入った薬剤は日本では、貼付剤の他、ぬり薬など使い易さを考え、いろいろな薬剤が販売されています。
この研究がさらに進み、本当に心臓の働きに良い成分だけが薬品として完成し、しかも貼り薬や、ぬり薬の形で使えるようになると良いですね。
なお男性ホルモンは瞬間の判断が必要な仕事の前に用いると判断力が上がるという研究があります。
その例として株の売買があげられていました。
あなたの街のドクターが答えます ~ それは1997年から始まった。-人の心と経済と- ~
女性せいかつ情報紙オントナ 2010年3月10日
それは1997年から始まった。-人の心と経済と-
暗いお話から始めて恐縮ですが…。
世界で最も読まれている医学雑誌の一つ「ランセット」によれば、ソ連が崩壊した後、同盟国だった東欧の諸国で、急速に国営企業を民営化した国と、そうではなかった国で死亡率に差があったそうです。
民営化を急いだ国は失業率が3倍になり、同時に男性の死亡率が40%以上高くなったのに対し、民営化を急がなかったチェコやポーランドでは、失業率の上昇も2%にとどまり、男性の死亡率も10%以下だったとの事です。
1979年イギリスではサッチャー政権が誕生。それまで停滞していた同国経済の立て直しが目的でしたが、目標は急速に達成されました。
しかしその裏で、失業率の増加、賃金の低下、貧富差の拡大、そして低所得者層の生活の困窮化が起こりました。
80年代に始まった大量の失業は、5年後に40―59才の男性の死亡率の倍増という結果で表われたと言われています。(「BMJ誌」=イギリスの医師会が発行する雑誌)。
では日本ではどうでしょうか。自殺者が目立って多くなったのは98年からです。それ迄「20年」以上も年間2万人台だった自殺者が、この年を境に3万人を越えたのです。
その前年97年末に起ったこと…。大銀行や大手証券会社の破綻でした。この頃から日本の経済構造の変革が声高に主張され始めた様に思います。
こうしてみると、その時々の経済情勢は人の心に大きな影響を与える事が分かります。
しかし、一方で明るい光も見えてきています。先のイギリスの例では、進学した人の気持が格段に前向きになったということから、「若年者の雇用面の不安のある時こそ進学率を上げるべき」との結論が出ています(「BMJ」)。
さて、今は新しい出発の季節です。
この時期、心の中で「進学」=「学を進める道」にチャレンジしてはいかがでしょうか。
この道に決まった道はありません。
しかし誰もが歩む事ができ、決して途切れる事のない道でもあります。
始めてみませんか。時間がかかっても…。マイペースで。
あなたの街のドクターが答えます ~皇帝をだました男。陰の主役は、ビタミンE!? ~
女性せいかつ情報紙オントナ 2009年7月8日
ビタミンEには多様な効能が。
ただし過剰摂取には副作用も。
秦の始皇帝は、紀元前220年、戦国時代だった中国を統一しました。ちなみに当時の日本は縄文時代から弥生時代に変わる時期でした。
何せ約25年で全国を統一した皇帝ですから、その権力は絶大だったようです。自分の居所を教えたというだけで側近全員を罰したり、当時の学術書を焼き払い、学者460人を生き埋めにしたりしました=焚書坑儒(ふんしょこうじゅ)。さぞや側近たちは、日頃から皇帝の顔色をうかがいつつ生活していたことでしょう。
しかし、そんな皇帝を堂々とだました人がいます。しかも、2回も。そのキーワードは「老い」でした。史記(秦始皇本紀)では徐ふつ(じょふつ)、日本では徐福という名で知られている人物は、海の先にある国に不老不死の神薬があると言ってまんまと皇帝をだましたのです。この徐福が目指したのが日本だったという「徐福伝説」があります。また、徐福が求めた神薬は、今考えると「ビタミンE」だという説もあります。
ビタミンEは、試験管の中でヒトの細胞を育てているときに加えると、細胞の寿命を延ばす力があります。つまり、寿命に関係するホルモンだということが分かっています。
さらにビタミンEには、身体に有害な作用のある活性酸素の働きを抑える作用もあります(抗酸化作用)。活性酸素とは、人間の身体に有害に働き、動脈硬化や老化・発がんなどと関係があると考えられています。また、ビタミンEはアルツハイマー病の進行を抑える作用もあるそうです。
さて、ビタミンEが多い食べ物は、胚芽米、小麦胚芽、大豆、落花生などです。よく考えると、これらはみんな中国原産か中国経由で入ってきたもの。まさか徐福が皇帝に献上せず日本に持ち込んだ…なんて事は無いでしょうね。
最後にビタミンEの副作用についても一言。
このビタミンは、妊娠中の過剰摂取は避けるよう指導されています。また、ビタミンEを摂り過ぎると脳出血が起こりやすいという研究もあります。やはり程々が大切なようです。
あなたの街のドクターが答えます ~自分の寿命が分かる時代が来たかも! ~
女性せいかつ情報紙オントナ 2008年11月5日
八五郎の運命は!?
これが本当の風前のともしび
のっけから死神というと気に障る人がいるかもしれませんが、落語の話なので。
ひょんな所で貧乏どん底の八五郎と死神が知り合いになります。
八五郎があんまり気の毒なので死神が知恵を授けてくれました。「医者の看板をかけてごらん」。八五郎にだけ見える死神が、病人の頭の側に座っていれば手遅れ、足元に座っていれば助かる運命だと言います。
足元に座っているとき「テケレッツのパ」と呪文をとなえると、あーら不思議。死神が消えて病人が元気に。これが評判を呼ばない訳がありません。八五郎はあっという間にお金持ちに…。
ある時、大店の主人が病気になって八五郎が呼ばれます。行ってみると、これはいけません。死神が枕元にいます。でもよく見るとウトウト居眠りしているではありませんか。
八五郎はその間に、病人の布団をそーっと動かします。死神が目をさますと、何と病人の頭は反対側。病人は治りましたが死神はカンカン。
怒った死神は八五郎を洞窟に誘います。そこにはたくさんのロウソクが…。
「こりゃ何だい?」と八五郎。「寿命さ」と死神。
中に今にも消えそうなのが一本。「これは誰のだい」「お前さんのさ」「何とかしておくれよ、助けてくれ!」「それじゃ消えそうな灯を別なのと取り換えるんだな」。八五郎が恐る恐る灯を移し換えようとした所にサーッと風が…。灯が消えた…。お後は落語で…。
空想世界から現実に
この人間の寿命が分かるというお話が、現実になるかも知れません。もっとも男性だけのお話ですが。
男性ホルモンの代表的なものにテストステロンがあります。これの値は全死亡、心臓血管系の病気による死亡、がんによる死亡と反比例関係があるそうなのです。
男性1万1606人を対象に研究した結果、血液中のテストステロンが低い程、死亡者が多いとのことです。また心臓血管系の病気やがんによる死亡率も高かったとのこと。死神のロウソクみたいな話ですね。
ところで、このテストステロンの塗り薬があります(日本にはありません)。
この薬を使うと寿命が延びるかどうか、今、研究中だそうです。
あなたの街のドクターが答えます ~更年期からは第二の青春~
女性せいかつ情報紙オントナ 2008年3月5日
団塊の世代が更年期を迎える時期となり、外来でも更年期についての質問が増えてきました。
更年期障害には幾つかの代表的な症状があります。
(1)上半身がカーッと熱くなる。時と場所に関係なく汗が出る
(2)頭痛、肩こりなどがある
(3)何となく気力がなくなる。
睡眠が浅い、朝早くに目が覚める。人付き合いが嫌になってきたなどです。
しかし、更年期の症状と思っても実は違う病気の時もあります。
(1)自律神経失調症
(2)心身症
(3)うつ状態あるいはうつ病などがそうです。
現在の状態が更年期障害によるものかどうか正しい診断を受けるためには
(1)自分の今の症状や悩みを正確に伝えること
(2)必要な検査を受けること(血液検査や心理テストなど)
(3)更年期障害用の薬剤を使用し、効果があるかどうかを見極めることが必要です。
これらの点については担当医から詳しく説明があるでしょう。
さて、更年期障害と診断されたら、どんな治療が勧められるのでしょうか?
これには注射剤、内服薬、貼付薬あるいはクリームのように塗る薬などから、効果と使いやすさ、起こり得る副作用などを考えながら薬剤が処方されることになるでしょう。
ただ、更年期障害の症状に、うつ症状が加わっているときは話が違います。症状を見ながら、うつ症状に効く薬がホルモン剤より優先されることがあります。
更年期障害は治療の後も大切です。
回復に個人差がありますが、その症状はほとんどの人が改善します。ここから次のステップが始まります。
もともと更年期障害とは、それまで出ていた女性ホルモンが大幅に減り、ホルモンの環境が変わったために起こるもの。
これに対し、今まで出ていなかったホルモンが出るために起こるのが初潮です。これもホルモンの環境が急に変わる時期には違いありません。ホルモンがさらに働くようになると女性らしさが増します。季節に例えると春でしょう。だから青春。
では、更年期は秋?しかし、秋は秋なりの重みがあるというものです。この世代、人生経験はそれなりに深くなり、若い頃より思慮深く、仕事に対する理解度が高くなります。
80代になって振り返ると、50~60代が最も充実した人生だったという人が多勢います。そうです。更年期は第二の青春でもあるのです。この時期を有意義に過ごすことが何より大切です。
あなたの街のドクターが答えます ~月経前に体調がわるくなる~
女性せいかつ情報紙オントナ
Q_ 40歳を過ぎた頃から、生理前日になると頭痛や吐き気の症状が続きます。
生理の時だけなので脳神経外科を受診したこともありません。閉経するまで続くのか不安です。
原因はあるのでしょうか?(45歳 主婦)
A_ 月経の前から身体的、あるいは精神的症状が出て、月経が来ると同時に症状が軽くなる「月経前症」という病気があります。
今のところ、月経周期に合わせて症状が出たり消えたりすることから、何らかのホルモンの関与が推測されています。この時に、出てくる身体症状として、頭痛、動悸(どうき)、吐き気、腹部の張り感などがあり、精神的な症状として、うつ気分や気分の減退、物忘れなどがあります。
ご質問の方は、症状が生理の時だけなので、この「月経前症」の可能性があるかもしれません。
治療は、薬による方法が主体です。
(1)ピルなどのホルモンを調整する薬
(2)「月経前症」の原因として、脳の中の神経のいろいろな命令を伝える物質(神経伝達物質といいます)に異常があるとの考えから、この神経伝達物質の働きもコントロールする薬(主に、抗うつ剤や抗不安剤)、
(3)漢方薬、などが使用されます。
医師は悩まされている方の症状、重症度、年齢、副作用の可能性などを考慮して、最も適切と思われる治療をお勧めするのが普通です。
ただし、注意しなければいけない点があります。頭痛の時は、脳外科の病気、吐き気の時は消化器系の病気など、それぞれの症状で専門医の診断が必要な病気が隠れていることがあることです。
また、年齢や環境、併用されている薬などによっては、「うつ状態」が本当の原因の時もあります。
まず、医師とよく相談されることが大切でしょう。
レッツ!けんこう ~子宮頚がんのウイルス~
読売新聞 2007年8月25日
Q- 子宮頸がんの原因がヒトパピローマウィルス(HPV)であるとよく聞きます。HPVはどうして感染するのでしょうか。
A- 主な感染経路は性行為と考えられています。しかし、「いつ」「だれと」と言うより、セックスそのものが感染の原因になると考えた方が良さそうです。セックスの経験があると、約50~80%の人が一度は感染するとの研究があります。しかしこのことは、セックスがある以上、感染は避けられないと言い切っているわけではありません。やはりパートナーは特定の人に決めておいた方が良いことが知られています。
Q- HPVは感染しても消えることがあるそうですが。
A- その通りです。ウィルス検査を続けると、約90%の人のウィルスが消えることが分かっています。このことは、女性の年齢が進むにつれて感染率が減るという調査と一致します。しかし50歳以上でも約10%の人に感染が持続しているというデータがあり、その意味では、何歳になっても子宮がん検査は必要ということになります。
Q- 最近、HPVに効くワクチンが開発されたと聞きました。これで子宮頸がんがなくなる可能性はあるのでしょうか。
A- 残念ながら、ワクチンはまだHPVに感染していない人には効果がありますが、既に感染している人には効きません。このためHPVの治療薬としての作用は期待できません。
Q- ワクチンが効かないとすると、何か良い方法がないでしょうか。長い間検診にだけ通っていると、不安を持ってしまいます。
A- 現在そのことが問題になりつつあります。HPV感染と言われた後、いつまで定期的検診が必要なのか、将来どうなるかといった不安が出てきます。
これには幾つかの解決策が考えられます。一つはHPVのタイプを調べ、がんになる可能性のあるタイプ(ハイリスク)か、そうではないタイプ(ローリスク)かを早く知ること。もう一つは、あまり通院が長くなる時は、子宮のがんの出来やすい部分だけを切除する手術(円錐切除)を受けることです。この方法は子宮本体が残るので、将来赤ちゃんを産むことも可能です。さて最後に大事な点を。
最近、子宮頸がんの死亡率が減ってきました。しかし若い女性の死亡率が逆に上昇しています。若い女性も積極的にがん検診を受けることが大切です。
レッツ!けんこう ~若い女性、高い感染率~
読売新聞 2007年5月26日
子宮頚がんとウイルス
Q_ 子宮頚がんの発生にウイルスが関係する可能性があると聞きました。
私も定期健診が必要と言われているため、関心があります。
A_ 子宮頚がんの原因にウイルスが関係しているらしいということは、以前から言われていました。約25年前にヒトパピローマウイルス(HPV)が子宮頚がんの人に高率に見つかることが分かってから、このウイルスとがんの関係の研究が急速に進んできました。
現在、子宮頚がんの95~99%はHPVが関係していると考えられています。
Q_ どういう経路で感染するのでしょうか。
A_ 今のところは性感染が最も多いと考えられています。ただそれ以外の感染の経路の可能性も否定できません。
Q_ 最近、若い女性の子宮がんが増えていると聞きました。HPVの感染は広がっているのでしょうか。
A_ 確かに若い女性にがんや、その前段階といえる異常(異形成上皮といいます)が増えてきているのは事実です。
私のクリニックでも、異形成上皮は若い女性ほど多く見つかる傾向があります。1番多く見つかるのが25~29歳、2番目が20~24歳です。
Q_ HPV感染もその年代に多いのでしょうか。
A_ HPVについては国や地域によって少し差があるようです。例えば日本では、20代の女性の20%が感染していることが分かっています。アメリカでは14~19歳の女性で24~25%、20~24歳で44~48%の感染率とのデータがあります。ただ、どこの国でも若い女性の感染率が高いことだけは事実のようです。
Q_ HPVに感染すると、がんやその前段階に必ずなるのでしょうか。
A_ 今のところ、そうは考えられていません。感染してもウイルスが消える人がいるからです。またHPV感染者は、将来がんになる可能性のあるタイプ(ハイリスクグループ)と、そうではないタイプ(ローリスクグループ)に分かれます。
HPVに感染しても、ローリスクグループなら、将来がんにならないで済みそうです。
Q_ この検査をすれば、今までのがん検診が必要なくなるのでは?
A_ そうとも言えません。
細胞診検査では現在の異常が分かります。これに対し、HPV検査は将来を推測できます。2つの検査を上手に利用することで、がんの早期診断を可能にし、有効な治療を進めることが出来るのです。
あなたの街のドクターが答えます ~子宮頚(けい)がん検診で「Ⅲa」といわれたとき~
女性せいかつ情報紙オントナ 2007年4月18日
子宮頚がん検診で、「細胞診クラスⅢa」と診断されて、相談に来る人が多くなりました。細胞診の結果は、ローマ数字でⅠ~Ⅴまでの5段階に分かれて出ます。このうちⅢだけは「Ⅲa」と「Ⅲb」に分けられます。大体の目安として、Ⅰ、Ⅱが正常、Ⅳ、Ⅴががんです。ⅢaとⅢbは“気を付けて”という意味と考えてよいでしょう。
ではクラスⅢaが出ると、次はどんな検査を勧められるのでしょうか。大体3ケ月後くらいにもう一度細胞診検査を受けることと、膣拡大鏡検査、そして必要なときは組織検査を勧められることが普通です。これは、例えると胃がんの集団検診で異常があると、胃カメラ検査(膣拡大鏡検査に相当します)を勧められます。胃カメラで異常がありそうな部分があれば、そこを切り取って組織検査を行いますが、婦人科の組織検査と同じ意味になります。この組織検査が、がんに関する最終的な診断になります。
ではクラスⅢaは、将来がんになる可能性があるのでしょうか。Ⅲaの説明の前に、Ⅲbについて先に話しておきましょう。Ⅲbは組織検査で見ると、高度異形成上皮(いけいせいじょうひ=初期のがんに似た形をしているが、まだがんにはなっていない状態)が見つかることが多くあります。この状態から約20%の人が、将来初期のがんになると考えられています。これに対し、Ⅲaの場合は将来がんになる確率が2~3%というデータがあります。逆にいうと、97~98%の人はそのままか、正常に戻るということです。
「それではⅢaはあまり心配のない状態か」というと、そうともいい切れません。それは、子宮がんの原因と関係があります。
最近子宮頚がんの原因はHPV(ヒトパピローマウィルス)の感染によるものがほとんどだろう、と考えられるようになってきました。このHPVの中に、将来がんになる可能性が高いハイリスクグループと、そうでないローリスクグループがあることも分かってきています。現在Ⅲaだとしても、ハイリスクグループのウィルスが感染していると、将来がんになる可能性があると考えられます。
このように、細胞診検査でクラスⅢaが出たときは、今までの診断法ではない新しい診断技術が育ちつつあります。ただ、新しい検査法であるだけに、その必要性、時期、費用などのほか、出た結果をどう評価したらよいかなど、主治医と詳しく相談することが大切です。
レッツ!けんこう ~患者夫婦の「人生」大切に~
読売新聞 2007年2月17日
不妊治療 心に残る言葉 -飯塚先生に捧ぐ
どの世界でも同じでしょうが、医療に携わっている人間は毎日が修練の場です。先輩や同僚だけではなく、日ごろ接する患者さんが先生でもあります。
今回は不妊治療で経験した話をします。まだ20代のご夫婦が患者さんでした。
いろいろ治療したのですが妊娠せず、体外受精を行うことになりました。普通、20代ですと妊娠率はかなり高いのですが、2回の体外受精でも結局、妊娠することは出来ませんでした。2回目の体外受精で妊娠していないことが分かった時のことです。
夫婦 「先生、これで不妊治療をやめにします」
私 「え、なぜですか?もう少し頑張ってみては」
夫婦 「先生も努力してくれたと思いますが、私たち二人も頑張りました。これから治療を続けて、妊娠することがあるかもしれませんが、そうでない可能性もありますよね」
私 「それはそうです」
夫婦 「では私たちは考えを決めています。これから治療を続けていて、もし妊娠しなければ治療を続けたことを後悔するかもしれません。これからの人生の方が長いし、二人だけの充実した人生設計を立てたいと思っています。」
このご夫婦の言葉は、私の不妊治療のバックボーンになっています。
私の大学時代の恩師に飯塚理八教授(旧制釧路中学出身)がおられました。日本の不妊治療の先駆者でもあり、指導者でもありました。昨年11月に亡くなりましたが、先生の常に言われていた言葉が耳に残っています。
「不妊治療は常に最新の知識を持って臨まなければいけません。でも、もし医学的にみて妊娠が不可能であると判断されたら、速やかにその旨を伝える事が医師の義務です。それは今後のご夫婦の生き方に大きな影響を与えることになるのですから」
これは医療に関する情報が、治療する側と、受ける側で共有されなければならないという意味でもあるでしょう。
不妊治療は年々進化をとげているのは事実です。あっと驚くようなニュースが流れる時もあります。しかしその恩恵を受けられるのは、限られた条件に合った人たちだけということもあります。実際、治療が進んでも不妊の方の割合は減っていないという調査もあります。
赤ちゃんを産むために頑張るのも大切でしょう。でも少し立ち止まって、人生をもう一度考えるのも大切ではないでしょうか。充実した人生を送るために。
レッツ!けんこう ~胎教~
読売新聞 2006年11月18日
Q_おなかの赤ちゃんが少し大きくなってきました。そろそろ胎教を考えています。
A_それは良い考えですね。胎教で大切なのは、まず赤ちゃんの立場で考えてあげることです。赤ちゃんが好みそうなことをやってあげる。反対に嫌がりそうなことはしないのが基本です。
絵本を読んであげたり、音楽を聴いたりしています。赤ちゃんの聴覚は比較的早く発達します。また脳の神経細胞は、妊娠7ヵ月ぐらいから発達を始めます。早い時期から聴覚を通して、脳に刺激を与えるようにしてあげると良いですね。
このほか、赤ちゃんの周囲の環境を整えるという意味で、家庭の中の温かい雰囲気が大切でしょう。お母さんの副交感神経(リラックスすると働く)が優勢になると、赤ちゃんも幸せです。
胎教と言えば音楽と考えて、クラシックを聴くようにしています。胎教に音楽はとても良いでしょう。クラシック音楽もそうですが、お母さんの好きな曲、心が休まるような曲なら何でも良く、別にクラシックにこだわることはありません。童謡でも子守歌でも、氷川きよしでも結構です。
でも、モーツァルトの曲が良いと聞きました。本当でしょうか。モーツァルトが胎教に良いのは確かでしょう。ただ科学的な根拠がはっきりしているわけではありません。
①モーツァルトの曲が嫌いだという人はあまりいない
②旋律に繰り返しが多く、心地よく聴ける
③高周波音が豊富で脳に達しやすく、良い刺激になる-などの説があります。
しかし、音楽の選択は義務ではありません。好みの曲を聴くのが一番です。
散歩したり、公園に行ったりするだけで、何かホッとします。これも胎教になるのでしょうか。それが本当の胎教ではないでしょうか。森の中を通るかすかな風の音、小川のせせらぎなどは、モーツァルトの緩やかな旋律の繰り返しと同じです。自然の胎教と言えるでしょう。
そのほか気をつけることはありますか。生まれたばかりの赤ちゃんは、みんな少しずつ個性が違うことが分かります。本当に泣き声一つで、おなかの中にいた時の環境が分かることがあるぐらいです。その意味で、お母さん方が、気持ち良く、楽しい妊娠生活を送られることが何より望まれます。
あなたの街のドクターが答えます ~卵巣チョコレートのう腫の治療~
女性せいかつ情報紙オントナ 2006年10月11日
Q_ 月経痛が重く、婦人科を受診したところ、「卵巣チョコレートのう腫(しゅ)」と診断されました。どのような病気でしょうか?
また、治療法についても教えてください。
A_卵巣チョコレートのう腫は、本来、子宮の内側にある子宮内膜組織が、卵巣の中にできる病気です。月経のたびにここに出血するため卵巣が腫れ、痛みなどの症状が出てくるのです。生理痛や性交痛など、子宮内膜症独特の症状が出るほか、不妊症の原因になったり、一部は将来、悪性腫瘍(しゅよう)に変わる可能性もあると考えられています。女性にとっては見過ごせない症状が出る病気のため、きちんとした治療が必要になってきます。
① 小さくて(直径3cm以下が目安)痛みがなく、不妊の原因にもなっていないときは、経過を見るだけで良い場合があります。
② 月経痛などの症状があるものの、あまり大きくないとき(大きさについては医師と相談を)は、薬剤による治療が進められる場合が多いようです。ただし症状の改善は見られますが、チョコレートのう腫が完全に無くなるわけではありません。治療後に再発する可能性もあります。
③ チョコレートのう腫がある程度大きい、あるいは急に大きくなった、明らかに不妊の原因になっているときなどは、、手術を勧められることがあります。手術は開腹手術、腹部に数ヶ所穴を開けて行う腹腔(ふくくう)鏡下手術、それと膣式にのう腫を処理する方法があります。
それぞれ利点と問題点があるので、医師とよく相談することが必要でしょう。この病気の治療法はたくさんあり、その選択が重要になります。一人ひとりに合わせた“オーダーメード”といえる、自分に合った治療法を選ぶことが大切です
レッツ!けんこう ~赤ちゃんのアレルギーを妊娠中の食事で予防~
読売新聞 2006年8月12日
Q_いま妊娠中です。最近赤ちゃんにアレルギー性の病気が増えてきていると聞きました。私もアレルギーがあるので心配しています。
A_最近の調査では、アレルギー性の病気(アトピー性皮膚炎など)が、3歳児の約40%に見つかっています。またその割合が少しずつ増えてきているほか、普通なら治る年齢になっても、治らないという傾向が出てきています。
Q_アレルギー予防のため、妊娠中に何か注意することはありますか。
A_両親のどちらかにアレルギーがあると、赤ちゃんにアレルギー性の病気が起こる確率が少し高くなります。妊娠中の食事などでこれらのアレルギーを予防しようという考えがあり、卵や乳製品を制限した方が良いという専門家もいます。しかし、食事とアレルギー発生は関係が無いという調査もあり、結論が出ていないのが現状です。
Q_完全な予防法は無いとしても、何か注意した方が良いことはありますか。
A_
① まず偏食をせず、バランスの良い食事をとることをお勧めします。
② 1日3食をきちんととると、アレルギー発生率が減るという調査があります。
③ 最近、アレルギー予防として和食が見直されています。みそ、しょうゆ、漬物などの発酵食品には、大豆や麦などのアレルギーを抑える作用があると考えられています。
④ 牛乳は飲み過ぎない方が良いでしょう。1日200ccくらいが目安です。
⑤ 卵は加熱してからというデータがあります。
⑥ リノール酸が多いインスタント食品はとり過ぎないように注意しましょう。
Q_妊娠中の食事以外に気をつけた方が良いことはありますか。
A_出来れば母乳をあげることが一番です。母乳の中にはアレルギーを抑える成分が入っています。また乳製品は将来のアレルギーの原因になることがあり、主成分が牛乳であるミルクより、母乳の方が赤ちゃんに優しいと考えられています。
Q_母乳が良いことが分かっているのですが…。お産のこと、母乳が出るかなどを考えると、いろいろ悩む時があります。
A_実は最近そういう悩みを持つお母さん方がとても多いのです。でも赤ちゃんは出生後、目が見えなくてもお母さんの乳首を探し当てます。赤ちゃんがサインを送ってくれます。お母さんは、それを見ているだけで良いのです。
レッツ!けんこう ~妊娠したら体重や食事の管理を~
読売新聞 2006年5月20日
Q_市販の妊娠判定薬で調べたら、妊娠反応が陽性になりました。早速病院に行こうと思っています。
A_そうですね。市販の判定薬の信頼性は高いのですが、病院で赤ちゃんが正常に成長しているか、子宮外妊娠をはじめとする異常妊娠がないかなどのチェックを受けることが大切です。
Q_赤ちゃんが順調に育っています。でも、とてもつわりが強いのですが。
A_つわりは妊娠すると約60%の人に起きます。しかし、どんなに症状がつらくても、12週より長く続くことはほとんどありません。ゴールが見えている訳ですから、もう少し頑張りましょう。ただし耐えられないときは、症状に応じて内服薬を処方されたり、点滴を勧められたりします。これらの治療でかなり改善します。
Q_少し赤ちゃんが大きくなってきました。友人から今が大切だからと、いろいろなサプリメントを勧められています。
A_妊娠中のサプリメントの摂取はあまりお薦めできません。妊娠中に足りなくなるのはカルシウムだけです(葉酸の摂取を勧められる場合もありますが)。むしろビタミンA・Eなど、過剰にとると、赤ちゃんに悪影響が出ると考えられる成分もあります。
Q_妊娠中、お酒やたばこはダメでしょうか。
A_これらは控えた方がいいでしょう。統計では、喫煙により流産率は2倍、早産率は3倍になるとされています。また、妊娠すると90%の女性が禁煙するというデータもあります。アルコールについては、どのくらいまでなら安全かということが分かっていません。しかし、お母さんの飲酒は、おなかの中で赤ちゃんも一杯やっているのと同じだと考えると、控えた方が良いと言えます。
Q_おなかが大きくなってきました。検診の際、食事に気をつけるよう言われました。
A_大切なのは、体重の管理とバランスの良い食事です。
①間食をしない
②食事を薄味にする
③果物はカロリーが高いので気をつける(意外と盲点ですが)-ことが大切です。
夕食時を含め、夜は果物をとらないようにしましょう。妊娠中の体重増加は、日本人の平均で10~11キロです。ただし、元々体重のあった人(55キロ以上)は、より厳重な管理が必要となります。
現在はたくさんの情報があふれています。過剰な情報に惑わされず、楽しい妊娠ライフを過ごせると良いですね。
あなたの街のドクターが答えます ~クラミジア感染症って~
女性せいかつ情報紙オントナ 2006年6月28日
今回の質問
クラミジア感染症は、一度かかったら再発しやすくなり、不妊の原因にもなると聞きました。どのような病気なのか、詳しく教えてください。(24歳 OL)
答え
クラミジア感染症は、今や10代から50代まで、幅広く広がっています。身近で感染する人が多いことから、この病気を簡単に考える風潮もあるようです。「セックスでかかる風邪」ぐらいに考えている人もいるようですね。しかし、クラミジア感染症を軽く考えるのは危険です。3つの注意点を挙げておきましょう。
①女性にとって治療が不十分だと、腹膜炎の症状が出ることがあります。この病気は、重症になったり、繰り返して感染すると、不妊の原因になることも。また、感染したまま妊娠すると、流産や早産の原因になることもあると考えられています。
②男性に感染があった場合は、精子を作る精巣や、精子を運ぶ輸送路に障害が起き、将来、男性不妊の原因になることがあります。
③ほかの感染症を起こしやすくなることがあります。淋(りん)病は、感染率が上がることが明らかになっており、子宮頸(けい)がんや、尖圭(せんけい)コンジローマの原因と考えられているパピローマウィルスの感染も起こりやすくなるのです。
また、HIV(ヒト免疫不全ウィルス)感染症も、クラミジア感染症と関係がある、との考えもあります。現在、HIV感染症の人は、1日2.1人の割合で増えていますが、先進国の中で増加しているのは日本だけです。
クラミジア感染症は、決して「風邪」のような病気ではありませんが、「万病のもと」になる可能性があるのです。気になるときは、産婦人科に相談を。
あなたの街のドクターが答えます ~卵管が原因の不妊について~
女性せいかつ情報紙オントナ 2006年3月1日
今回の質問
結婚して5年、まだ妊娠しないので婦人科を受診。卵管が詰まっているため、妊娠しづらいと言われました。治療法の1つとして体外受精を勧められましたが、ほかに方法がないか教えてください。(35歳 主婦)
答え
卵管が詰まった人の治療方法は、大きく分けて2つあります。一つは体外受精、もう一つは詰まった卵管を通すようにする方法です。
卵管を通るようにする方法には、「手術」と「FTカテーテル法(卵管鏡下卵管開口術=らんかんきょうからんかんかいこうじゅつ)」があり、最近はFTカテーテル法が広まりつつあるようです。これは子宮の方から卵管の中に“バルーン”という細い管を入れ、詰まっている卵管を少しずつ広げる方法。腹腔(ふくこう)鏡でおなかの中を観察しながら行うと、さらに治療効果が高まる可能性があります。
この方法の利点は、一度卵管が通ると、再癒(ゆ)着がない限り、2人目、3人目も自然に妊娠が可能になる場合があることと、保険が適用になること。
欠点は、卵管の詰まり方によっては治療効果が落ちることと、治療可能な病院が限られているということです。
体外受精は、すでに確立された治療法です。排卵誘発剤を用いて卵の入っている卵胞を大きくし、排卵の準備ができたと判断された時に、この卵胞から卵を取ります(採卵といいます)。この卵の入っている容器に精子を入れ受精させ(体の外で受精させるので体外受精といいます)その受精した卵(受精卵)を子宮に戻す方法です。体外受精は20年以上の歴史があり、妊娠率などのデータがそろっています。
不妊治療を受ける人は、これらのデータや治療手順、考えられる副作用など、主治医から詳しく話を聞くことが大切です。
あなたの街のドクターが答えます ~細胞診クラスⅡって危険? ~
女性せいかつ情報紙オントナ 2005年10月26日
今回の質問
子宮がん検診を受けたところ、「クラスⅡ」と言われました。昨年は「クラスⅠ」でしたが、ⅠからⅡになったのはとても気になります。
将来がんになる可能性があるのでしょうか?(50歳 主婦)
答え
結論から先に申し上げると、今現在では心配ないと思います。子宮がん検診は、がんのできやすい部分の細胞を採って顕微鏡で検査します。結果は、クラス分類といって「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」(「Ⅲa」と「Ⅲb」に分かれます)「Ⅳ」「Ⅴ」の5段階で表されます。
このⅠ~Ⅴまでの結果はそれぞれ意味があるのですが、おおまかに次の3つに分けて考えると分かりやすいでしょう。
○クラスⅠ、Ⅱ…異常なし
○クラスⅢa、Ⅲb…気を付けて
○クラスⅣ、Ⅴ…がん、またはがんの疑い
ご質問の方のクラスⅡは異常なしのグループに入ります。ではなぜ、「異常なし」なのにⅠ、Ⅱがあるのでしょう。
Ⅰはまったく異常のない状態です。Ⅱは基本的に異常はないのですが、炎症やホルモンのバランスの崩れが起きて、顕微鏡レベルで、やや活発な活動を示す細胞が現れる状態をいいます。
Ⅲあるいは、Ⅳ・Ⅴのグルーブでも活発に活動する細胞が現れますが、Ⅱの細胞とは明らかな差があります。これらの差は、細胞を検査する専門家の目で見ると、比較的容易に区別が可能です。
Ⅱの方のほとんどは、時間が経過し、炎症などの原因が治まればⅠになると考えてよいでしょう。
なお検診でクラスⅢa以上が見つかった場合は、医師から詳しい説明があるのが普通です。現在異常なしの方でも、健康管理のため、定期的な検診を受けることをお勧めします。
レッツ!けんこう ~システム確立高い妊娠率~
読売新聞 2006年(平成17年) 1月21日
不妊治療
Q_結婚して一年半たちました。そろそろ赤ちゃんが欲しいのですが。
A_世界共通のようですが、結婚後1年で約80%のカップルが妊娠されています。2年では90%です。
Q_それでは、そろそろ病院に行く時期ですね。
A_そうですね。それともう一つ大事なことがあります。妊娠率に差はないのですが、女性の年齢が高くなるにつれて、流産率が高くなるという点です。その意味で、女性の年齢がある程度高ければ(37.38歳ぐらい)、早めに相談に行くことも大切です。
Q_病院に行くと、まずどんな話があるのでしょうか。
A_まず検査の話があります。女性側では、月経周期に合わせた検査もありますので、検査の方法、目的、手順等について詳しく話を聞きましょう。
Q_どんな検査がありますか。
A_統計上、赤ちゃんが出来にくい4大原因というのがあります。
①排卵の異常
②卵管の異常
③精子の異常
④子宮内膜症(重症タイプ)です。
それ以外の原因を含めて、全体的に検査を受けるのが普通です。ただ、検査中に約20%の方が妊娠されます。
検査自体が治療を兼ねる部分があるからだと考えられています。
Q_検査で異常が見つかると、そこを治療するということですね。
A_その通りです。しかし治療をしても妊娠しない時、原因がはっきりしない時もあります。そうした時は、医師から改めて治療について話があるでしょう。
Q_原因が分からなければ治療は難しいのでは?
A_不妊治療の場合は、そうとは限りません。原因の有無とは別に、治療のシステムが比較的確立されているからです。
①排卵日をみてのタイミング指導
②排卵誘発剤の使用
③人工授精
④体外受精-という順に治療が進められます。
例えば、①に比べ③は2~4倍妊娠します。④は③の1.5倍です。
Q_ではいきなり体外受精をする方が良いのでは?
A_そうとも言えません。実は不妊治療では、人工授精までの段階で、約70%の方が妊娠することが分かっています。通院の期間、薬剤や治療の際の副作用等を考えると、①~④に進んだ方が合理的と考えられます。ただこのほかに、不妊期間、女性の年齢、他の合併症の有無等が、治療を考える上での大切な要素になります。
治療計画については、副作用を含め、医師と詳しく話をすることが大切です。
レッツ!けんこう ~心と体 バランス大切~
読売新聞 2005年(平成17年)10月1日
今日は中学3年生の女の子がお母さんと来院されました。
母・・・娘の生理が不順で,今月で4か月ありません。昨年まではきちんとあったのですが。
娘・・・勉強もあるし、部活もあるので・・・・。
母・・・それにダイエットもしているようで、このごろやせてきたみたいです。
娘・・・そんなことないよ。2キロしか減ってないよ。
母・・・寝るのも遅いわね。もっと計画的に一日を過ごしてみたら。
娘・・・勉強が終わったらすぐ寝るという訳にはいかないの。やりたい事もあるし。
医者・・・分かりました。ところで睡眠は何時間ぐらいですか。部活は何をしていますか。
娘・・・睡眠はだいたい6時間ぐらいです。部活はバレーボールをしています。
母・・・熱心な先生で、日曜も練習に行くんです。娘は休みたい日もあるようなのですが。
医者・・・いろいろ問題があるようですね。一つずつ考えてみましょう。
問題点の一つは部活が忙しいことです。結局は睡眠時間にしわ寄せがきているみたいですね。体力の低下や睡眠不足は、若い女性の生理不順の原因になります。
一回の生理で約30~60ccの出血があります。鉄分でみると約15~30ミリグラムの喪失ですが(男性は一日で1ミリグラム)、次の生理までにこれを回復しなければなりません。それが無理と判断されると、生理を起こさないで体力を温存しようという力が働いてしまいます。
部活に熱心な先生ほど、こういうことが起きる傾向にあります。「熱血指導」は良いのですが、精神と体のバランスを考えて指導することが大切です。
二つ目はダイエットです。若い人はダイエットが過激に、そして期間が長くなるほど、副作用が出た場合、その後の改善に時間がかかる可能性があります。
しかしダイエットの問題は複雑で、その裏には心療内科的な問題や、重大なストレスが潜んでいることもあります。
どうしたら良いか、本人や家族が戸惑う時は、素早く医師と相談されると良いでしょう。相談しているうちに、内科、心療内科、産婦人科など通院すべき科がはっきりしてきます。
医者・・・さて、今日は簡単なホルモン検査と貧血の検査をしましょう。一週間後に結果が出ますから、それを見て治療計画を立てましょう。
レッツ!けんこう ~子宮内膜症とは~
読売新聞 2005年(平成17年) 6月18日
![]()
月経痛があり、診察を受けたら子宮内膜症と言われました。どんな病気でしょうか?
![]()
子宮全体がはれたり、卵巣がはれたりして、月経痛や月経量の増加などの症状が出る病気を子宮内膜症といいます。貧血や不妊、腹痛、腰痛、セックスの時の痛みなどいろいろな症状が出る時があります。また病気自体は良性でも、少しずつ症状が進行する可能性があるため、早い段階で診断と治療が望ましい病気です。
![]()
子宮内膜症になりやすい人はいますか?
![]()
遺伝する病気ではありませんが、子宮内膜症が母親や姉妹のどちらかにあると発生する確率が高くなると考えられています。月経が8日以上続く方、周期が27日未満の方は比較的なりやすいと言われており、これらに当てはまる方で、月経痛のある方は一度検診を受けた方が良いでしょう。
![]()
鎮痛剤はなるべく使用せず我慢しています?
![]()
生理痛が強いのに我慢し続けるのはあまりおすすめ出来ません。日常生活に支障が出たり、我慢したりするうちに子宮内膜症が進行しては困ります。医師と相談して①鎮痛剤だけで良いのか②子宮内膜症本来の薬を使用した方が良いのか③何らかの手術的治療(多数の選択肢があります)が必要か判断が大切です。
![]()
不妊の原因になる事はありませんか?
![]()
不妊症の原因の約15%は子宮内膜症が関係しているとの研究があります。おなかの中を観察する腹腔鏡検査の際、症状がなくても、約半数の方に子宮内膜症が見つかります。この時に治療すると妊娠率が高まることが分かっています。
![]()
がん化する心配はありませんか?
![]()
高い確率ではありませんが、がん化する可能性もあると考えられます。①卵巣が大きくはれている②血液中の腫瘍マーカーが高い③超音波や磁気共鳴画像装置(MRI)検査で異常な像が認められる時は、精密検査や定期的検査をすすめられるのが普通です。
![]()
再発する可能性のある病気でしょうか?
![]()
子宮内膜症は女性ホルモンの影響をうける病気のため、ホルモンが働く年代の方は再発の可能性があると考えられます。再発の際は①前回用いた薬を再度用いる②薬をかえる③手術するなどいろいろな治療方法がありますが、治療効果や副作用など医師と詳しくお話することが大切になります。
からだと健康 ~生理痛~
読売新聞2005年(平成17年) 3月5日
■生理痛にもいろいろあります。
生理痛は、一度子宮の中に出た出血(月経血)が、子宮の外に押し出されるために起こるものです。
しかし、生理の時よりも、生理の前や後の方が痛かったり、生理の時の不快な気持ちが気になったりするという方もおられます。
これらの症状も、広い意味の生理痛と考えて良いでしょう。
■注意が必要な生理痛があります。
若いうちから生理痛があっても、 成人すると良くなったり、妊娠や分娩後に痛みがなくなる時があります。
しかし、すべての生理痛がそのようにうまく改善するとは限りません。
だんだん症状が悪くなる時もあります。
次のような症状が出てきたら注意しましょう。
・生理痛がだんだん強くなる
・鎮痛剤の量が増えてきた
・学校に行けない、職場で仕事にならない
・生理の量が増えてきた
・生理が長く続く
・おなかにしこりを感じる
・生理の前になると気分が落ち込む
・赤ちゃんが欲しいけれどなかなか出来ない。
■生理痛と病気
①診察で異常がない時
このような時は、主に鎮痛剤を内服しているうちに、自然に良くなる時があります。
しかし、何もないように見えても、不妊の時は話が別です。
不妊の方で、生理痛などの自覚的な症状が軽くても、おなかの中をみる「腹腔鏡」検査を行うと、約50%の方に子宮内膜症が見つかります。
症状が軽いと言っても、油断は出来ないということです。
ちなみに、この腹腔鏡検査の後に約50%の方が妊娠されるというデータがあります。
②子宮内膜症
生理痛がおこる代表的な病気です。
・少しずつ進行する時があること
・不妊症の原因になる可能性があること
・将来癌になる可能性があること
などから、子宮内膜症が疑われる時は、慎重な診察と適切な治療が必要となります。
治療は大まかに言えば次のようなコースで進むのが普通です。(下図参照)

③子宮筋腫
子宮筋腫で生理痛がおこる時があります。
子宮筋腫に対しては、筋腫を小さくするお薬を使ったり、症状に合わせたいろいろな手術療法など、きめ細かな治療方法が考えられています。
④気持ちの持ち方に問題がある時があります。
精神的なこと、ストレスなどが原因と考えられる生理痛があります。
鎮痛剤や漢方薬が用いられますが、心療内科的なお薬が効く時があります。
■生理痛と日常生活
痛みが強いのに、お薬を使わず我慢する方がおられます。
しかし、日常生活に影響が出るくらいの痛みの時は、むしろ、お薬を上手に使った方が良いと考えられます。
適度な運動は、生理痛に良いということが分かっています。
日ごろ、積極的に身体を動かすようにしましょう。
婦人科の炎症(最近クラミジア感染が問題になっています)が、生理痛を悪化させる時があります。
感染症はきちんと治療しておきましょう。
からだと健康 ~生理以外での出血~
読売新聞2004年(平成16年)11月6日 掲載
生理以外に出血があると、女性はとても驚きます。
しかし、出血量が少なかったり、すぐ止まったりすると、つい病院に行くのが億劫になってしまう時があります。
出血は命にかかわる事でなくても、放っておくと人生に不利に働く事もあり、「診察を受けて」というサインと考えた方が良い時があります。
出血の主な原因をあげてみましょう。
① ホルモン系統の異常。
② 感染症(クラミジア、淋病等)
③ 妊娠に関係したもの。
④ 子宮筋腫、内膜症等。
⑤ 悪性の病気
⑥ その他、内科の病気等。
◆ホルモンバランスの崩れ
表のように、思春期の時の出血はホルモンバランスの崩れが多いのですが、原因として過度な部活や睡眠不足の時があります。
また最近は、本来比較的ホルモンバランスの崩れにくい性成熟期の女性の不正出血が多いことが目立ちます。
背景に男性と同じ環境で頑張らなければいけない事があるかも知れません。
このような症状が出た場合は、心身を休ませる心遣いが必要になります。
女性ホルモンを通しての「注意信号」と言えるでしょう。
更年期以後の出血は、ホルモン不足が原因の炎症の事が多く、黄色のおりものを伴う時があります。
◆感染症
感染経路については、最近十代から見つかる事が珍しくなくなってきました。
黄色や水様性のおりものと、少量の出血、接触出血等が主な症状です。
クラミジア感染では、放っておくと8~30%の女性で、おなかの中に炎症が広がる可能性があります。
これは将来の不妊と関係する事があり、注意が必要です。
対策としては、次のことが挙げられます。
① お薬をきちんと使う事
② 治ったことを確認する事。
③ パートナーも病院に行く事が大切です。
◆悪性の病気
子宮の出口に出来る子宮頸癌は、最近パピローマウイルスというウイルスの感染が問題になっています。
また、若い女性の子宮癌が増えており、当院の統計では三十代の方が一番多く見つかっています。
初期の癌では、少量の出血や接触出血が特徴的です。
早期に発見された癌は、子宮の出口の部分の切除だけで済む事が多く、将来、赤ちゃんを産む事も可能です。
子宮の奥に出来る体癌は、生理以外の出血が最初の症状の時があります。
ただし出血=体癌ではありませんので、冷静に対応しましょう。
気になる症状からみた疾患 ~貧血~
薬事日報社
1 はじめに
貧血は日常よく見かけられる疾患ですが、それを引き起こした病気の原因や貧血の際の赤血球の形の違いなどから、普通いくつかの種類に分類されます。その中で多いのは、やはり血液中の鉄分が不足して起こる鉄欠乏性貧血で、貧血全体の60~70%を占めると言われています。また、この鉄血欠乏性貧血の約80%が女性に認められると言われています。ここでは、私のクリニックでの症例を中心にお話しします。話の順序として、最初に貧血の診断基準について、2番目に貧血と患者さんの年齢との関係について、3番目は男性に比べて女性に貧血が多いのはなぜかということについて、4番目に貧血の原因についてお話しします。そして最後に治療と生活指導について論じることにします。
2 貧血の診断基準
まず貧血の診断基準についてですが、これにはいろいろな基準があります。しかしヘモグロビン濃度を基準とするのが普通で、WHO基準では、成人の男性でヘモグロビン13g/dl以上、女性で12g/dl以上、妊婦では11g/dl以上が正常値とされています。妊婦のヘモグロビンの正常値が妊娠していない女性に比べて低いのは、妊娠中血液が薄くなるのが生理的な状態だからです。それはどういうことかと言うと、妊娠中は全体の血液量は増加するのですが、その際、赤血球の数の増加より水分である血漿量の増加のほうが多いために見かけ上ヘモグロビン濃度が低くなるからです。したがって妊娠中の貧血症状については、本当は思ったより貧血ではないこともあるということに注意をはらう必要があります。
3 貧血の年齢との関係
次に貧血と患者さんとの年齢の関係についてお話しします。私のクリニックでは平成6年1月から12月までの1年間で、妊娠している人を除いて、ヘモグロビンが11g/dl以下であった人は124人いました。その人たちを10歳ごとに区切ると、20歳以下では3人、20歳代で14人、30歳代で27人、40歳代では67人と、年齢が増すにつれて貧血の人が増えてきました。しかし、逆に50歳代になりますと貧血の人は11人に減り、60歳以上では2人になっています。
このように、だんだん年齢が上がってくるとともに貧血患者はその数を増し、40歳代でピークとなるのがわかります。ところが、この貧血患者の数は50歳代になると40歳代の6分の1へと激減しています。これはなぜでしょうか。最大の理由は月経にあります。50歳を過ぎると月経がなくなり、出血の危険にさらされる人の数が減るからです。もう一つの理由は、40歳代に多く認められる出血を伴う病気のためと考えられます。このことについては後でまた改めてお話しします。
4 貧血の男女差
次に貧血の男女差についてお話しします。前にも述べましたように、貧血の中でもっとも多い鉄欠乏性貧血の患者さんの80%は女性と言われています。ではなぜ女性に貧血が多いのでしょうか。
ひとつには月経のためと考えられます。女性は1回の月経周期で約30~60ccの出血をしますが、これは鉄に換算すると15~30mgの喪失を意味します。成人男子の1日の鉄喪失量が約1mgですから、この出血の程度がどれほど多いか理解できると思います。また妊娠の際にも大量の鉄分が要求されます。赤ちゃんの成長のためには鉄分が必要なのですが、全妊娠経過を通じて約500mgもの鉄分が必要だと言われています。これも先程述べました成人男子の1日の鉄喪失量1mgに比べると、実に膨大な数字だということがわかります。妊娠中のお母さんの十分な食事の管理が必要だとされるゆえんです。
5 貧血の原因疾患
次に貧血の原因となるべき疾患について考えてみましょう。貧血の原因は年齢と関係することが多いため、ここでは年代別に考えてみたいと思います。
まず先程、20歳以下でも貧血が認められると言いましたが、この年代では食事が不規則なために起こる貧血や子宮内膜症(この病気は子宮や卵巣が大きくなったり、月経痛が出てくるものです。)あるいは、卵巣から出てくる卵胞ホルモンと黄体ホルモンのバランスがとれない機能性出血の患者さんが認められます。これが20~40歳代までの成熟期では、子宮内膜症や機能性出血の他にも子宮筋腫の人が同じくらいの割合で認められるようになります。そして40~49歳の更年前期から更年期にかけては、子宮筋腫のための貧血が圧倒的に多くなり、貧血患者の50%を越えるに至ります。
一方、この年代から悪性腫瘍による貧血が目につくようになります。50歳代の閉経期では子宮筋腫がやはり多いのですが、悪性腫瘍による貧血の比率は少しずつ増加してきます。これが60歳以上の高年期になりますと、再度機能性出血の比率が増すのですが、同時に悪性腫瘍のための貧血の割合が著しく増加してきます。このように年代ごとに貧血の背景が変わってくることから、貧血の治療についてはきめ細かな配慮が必要だということがわかると思います。
6 貧血の治療法と食事指導
最後に貧血の治療と食事指導についてお話しします。鉄欠乏性貧血の場合、いかに効率的に鉄の吸収を良くさせるかが治療のポイントになります。食事療法や鉄剤による治療がありますが、一度出来上がってしまった貧血を食事だけで回復させるのは難しく、鉄剤による治療が第一選択となります。鉄剤は一般のクリニックでは経口か静注かで投与されますが、双方とも治療効果にあまり差はないとされています。ヘモグロビンで言えば、1日0.2g/dl程度の割合で増加すると言われています。
しかし、皆さんがよくご承知のように、鉄剤の経口剤は胃に対する負担が強く、内服できないという訴えがかなりあります。したがって胃の保護を同時に行うことが大切です。まず薬剤は食後に服用させることが望ましい他、健胃薬の併用は好ましいと考えられています。一方、制酸剤は用いるべきではありません。これは制酸剤が鉄の吸収を妨げることがあるとされているからです。また、ビタミンCの併用は鉄の吸収を良くすると考えられています。もちろん、コーヒー、紅茶、緑茶などは控えるのが普通です。この胃の副作用は、通常投与量に左右されると言われていますので、服用しにくい人は当初は薬剤の1日の投与量を少なくし、その後除々に増加させると良いとされています。またお互いに吸収を阻害し合うことがあるため、テトラサイクリン系の薬との併用は避けなければなりません。薬剤は通常貧血の改善が認められる4~8週間は内服が必要と考えられています。
しかし、その後の血液検査で貯蔵鉄の改善が認められるまで、さらに4~12週間の投与が必要との考え方もあります。
食事の注意に関しては、肉や魚に含まれるヘム鉄の方が殻物や野菜、海草などに含まれる非ヘム鉄に比べて吸収されやすいことから、肉や魚のほうが優先されるべきだと考えられています。ただ、貧血に良いとされるレバーは、最近飼料中に含まれているビタミン過剰の問題から、妊娠している人はむしろ取りすぎに注意すべきだとの指摘があります。同じ意味で妊娠中は脂溶性ビタミンであるA・D・E・Kなどは使用が制限されなければいけません。また胃液の分泌が高まるほど鉄の吸収が良くなると考えられているため、香辛料や適度のアルコールの摂取は良いとされています。なお、赤ワインは、その中に少量の鉄分が含まれているために、他のアルコールに比べて優れていると言われています。以上、鉄欠乏性貧血を中心に貧血について話しをしました。貧血への対応として、背景となる原因疾患を考慮に入れて適切な薬剤が十分に用いられること、さらに患者さんの健康を管理するという意味で、相応の食事指導がなされることも大切であろうと考えられます。
不惑の健康クリニック ~男性にもある更年期障害のお話~
慶応112年 三田会会報 第4号
今日は更年期障害のお話をしましょう。更年期障害は文字通り更年期に起るさまざまな身体的、精神的異常を言います。これは50才近くになるとそれ迄出ていた卵巣ホルモンが急激に減る為に、卵巣に対して命令を出す脳の中枢ホルモン(ゴナドトロピンと言います)が急に増加する為に起る症状と考えられています。しかしこれは必ずしも女性特有の病気ではありません。男性にも立派に起り得る病気なのです。
最近朝になると後頭部が痛かったり、肩こりが気になったりしませんか。人と大事な話をしている最中上半身がカーっとなる一方で冷汗が出たり、今日は朝から仕事をしたくないなぁと思った事はありませんか。これらは女性の更年期障害に実によく似た症状なのです。 男性に更年期障害があると言われると「本当?」と思ってしまいますが,医学的にも理屈のある事なのです。少し専門的になりますが、その理屈(由)とは男性でも女性ほどではありませんが更年期になると性ホルモンが減少して、前途のゴナドトロピンが増加してきます。これが原因となる可能性があります。また更年期障害と言っても、女性ホルモンが関与しているのはそのうち45%位で、他はどうも精神的な背景が原因となっているのではないかと考えられている事も理由として挙げられます。
従って何かストレスになる様な背景があれば、男性でも女性と同じような症状が出ても不思議ではないという事になります。会社のトップであれば会社の将来が気になる、中間管理職であれば上にも下にも気をつかう、嫁さんには冷たくあしらわれる、子供達には相手にされない、となれば症状が出てもおかしくはありません。全く困った年代と言うものです。 ではこれを克服するにはどうすれば良いか、ポイントを幾つか挙げておきましょう。
1. まず良い医者と出合う事、良い医者の手持ちのカードがなければ良い医者を紹介してもらうルートを持つ事。
2. 良い相談相手を持つ事。
3. 散歩、太極拳、ヨーガ等運動は可。
4. 何と言っても十分休むこと。週休3日を目指せば2日位休めるかも知れない。私達中年世代こそ人生を旅に使っても良いのでは。
加齢と外性器の変化について(家庭医学講座講演会の講演から)
琴似産科婦人科クリニック 酒井 潔
まず患者さんをご紹介いたします。
年齢 56歳 職業 なし、家庭の主婦
「どういうことで、病院へ来ましたか」という質問にたいして、「昨日、トイレでテッシュに血が付いているのに気付き、心配で病院に来ました」ということでした。
出血の量は多くはないが、赤い血はテイッシュについていたそうです。詳しく聞いてみると、さらに、1か月くらい前より、黄色っぽいおりものが増えて、不愉快な臭いがあるのに気付いておりました。
それから、膣の周りに、しょっちゅう、痒みがあり、時にはヒリヒリした痛みを感ずることもありました。 ここ数年、子宮癌の検診は受けてなかったそうです。
閉経は49歳でした。つまり、生理がなくなってから7年を経過しております。
子供は2人、ご主人は健康です。
そこで、子宮癌の検査を含め、診察することにしました。
内診しようとすると、膣は狭くて、内診する指が1本しか入りません。普通は、人差し指と中指の2本の指が挿入可能ですが、この方のように、閉経後7年もたつと、萎縮して、狭くなる人もおります。そこで、人差し指1本で内診を進めましたが、子宮は正常の大きさ、両方の卵巣も特に大きくはなく、子宮と卵巣はともに内診上は、異常なしと思われました。
つぎに、膣鏡といってアヒルのくちばしのような形をした器械で、膣を開き、観察してみました。すると、膣壁つまり膣の壁を構成する膣の粘膜は点々と内出血があり、子宮の入り口にも粘膜からの出血が認められました。そこで、子宮の入り口から細胞をとり、子宮癌の検診を行いました。
また、女性ホルモンの不足がうかがわれるので、血液中の女性ホルモン、エストラジオールを測定しました。
このような状況から、臨床診断は萎縮性膣炎としました。
この萎縮性膣炎というのは、どうして起こるのかと言いますと、原因は、一口でいえば、女性ホルモンの不足によるものであります。そこで治療は、不足しているホルモンを補うために、ホルモン補充療法を行いました。今回はホルモン剤を含んだ膣錠を膣のなかに挿入し、口からもホルモンの錠剤を飲んでもらうことにしました。この膣錠の挿入とホルモン剤の飲み薬の2本立てで、しばらく通院してもらうことにしました。
1週間後にわかりましたが、子宮癌検診の結果はガン細胞は出ていませんでしたが、萎縮性の細胞が認められ、やはり、萎縮性膣炎という診断でした。
血液中のホルモン検査ではエストラジオールの値が普通は30pg以上あるべきところ、10pg以下という結果で、かなりの女性ホルモンの不足が目立ちました。
ホルモン補充療法として、エストリオールの膣錠と飲み薬で治療を行っておりました。数回の洗浄で、膣からの出血はおさまり、外陰部のかゆみ、ヒリヒリ感も改善してきました。
ところが、2回目の洗浄の時、前回は言ってなかったが、「実は、性生活がつらいのです」と。「痛くて性交がスムーズにできない。夫には悪いが最近は断っているのです。どうにかならないでしょうか」ということでありました。
これも、萎縮性膣炎のひとつの症状で、とりあえず、潤滑剤として、KYゼリーを1本あげまして、性交の直前これを、局部に塗って下さい、それから、膣錠と飲み薬を続けることによって、性交の苦痛も和らぐでしょうとお話ししました。
本日は、そういうわけで、加齢と外性器の変化というテーマに沿って、萎縮性膣炎をとりあげてみました。
原因と症状
まず、萎縮性膣炎がどうして起こるかと言うところからお話ししようと思います。 根本的な原因は女性ホルモンの不足です。
日本人の場合、女性の閉経年齢、生理が止まる年齢は、平均50歳といわれております。生理が始まる年齢は昔に比べて若干早くなる傾向にあります。しかし、閉経年齢は、ほとんど、時代によって変化なく、この100年間くらい、いつも50歳前後でした。
卵巣には2つの働きがあって、1つは卵を作って毎月1個ずつ排卵させる働き、もう一つは、女性ホルモンを作って血液中に分泌する働きがあります。この2つの働きは、歯車の両輪のように、一方がダメになると、もう一方もダメになります。つまり、排卵がなくなると、ホルモンの作られ方も悪くなる。
閉経するということは、卵巣が働かなくなって、排卵がなくなるわけですが、同時にホルモンの働きも悪くなる。
排卵は、あるか、ないかで、いわゆるオール オア ノンで、なくなったら、全くありません。それに比べて、ホルモンの方は、排卵がなくなったらといって、ピタッとゼロになるわけではありません。
確かに、閉経に伴って、女性ホルモンを作る場所は、主に卵巣ですがそのほかに副腎というところがあります。また、少量ですが、脂肪組織でも女性ホルモンは作られます。そして、閉経後の女性ホルモンの価は、非常に個人差のあることが知られています。
つぎに女性ホルモンのはたらきについて述べてみます。
今回のテーマにある膣に対する作用としては、女性ホルモンは膣粘膜を厚く、丈夫にする。だから、閉経になって、女性ホルモンが不足すると、膣の粘膜が薄くなって、弱くなる。膣のひだひだがなくなって、のびが悪くなる。そして、ときには、あまりにも薄くなって、毛細血管から出血が起こる。膣の粘膜の下に出血が起こる。粘膜下出血です。点々と霜降り状に出血のあとが見られる。また、そういうときに内診とか、性交などの機械的な刺激が加わると、容易に粘膜が傷付いて出血する。ときには今回のようになんら原因がなくてもある日突然に出血することもある。
そればかりではありません。膣に潤いがなくなる。膣の分泌物が減って、乾いた状態になる。従って、内診の時に指が入りにくく、普通は2本は入るべきところ、1本しか入らない。性交の時、なかなか濡れてこない。ペニスが入らなくて、無理に入れようとすると、痛い。というようなことがあります。 そうなると、膣の粘膜が薄くなった上に乾いた状態になると、ちょっとした刺激でひりひりした痛みを感ずることがある。またときには、痒みが発生する。その痒みもなかなか頑固で、夜も昼も悩まされることになります。
第2に、膣に住む細菌に対するに女性ホルモンの作用です。
膣の中は、全く細菌のいない無菌状態ではありません。
大腸の中に大腸菌がいるように、膣の中には乳酸桿菌、発見した人の名前を取って、デーデルラインの桿菌ともいいます。
この乳酸桿菌は膣粘膜のグリコーゲンを分解して乳酸にし、その分解のエネルギーで生活し、繁殖しています。この乳酸桿菌がたくさんいると、乳酸がたくさんでてきます。乳酸は名の通り酸ですから、酸っぱい。健康な女性のおりものは酸性で、すっぱい臭いがします。膣の中が酸性ですと、ばい菌の繁殖に不適当で、乳酸桿菌以外の菌は皆死んでしまう。外から来たばい菌は繁殖できない。これが膣の清潔な状態で、酸っぱい臭いは、これはおりものが健康であることの証拠です。
女性ホルモンが不足すると、膣の粘膜は萎縮して、細胞に含まれているグリコーゲンは少なくなります。そうすると、それを栄養源にして生きている乳酸桿菌は住み難くなって減少してしまう。そうすると、膣内の酸度が下がって中性とか、アルカリ性になってしまう。その結果、雑菌、例えば大腸菌、ブドウ球菌連鎖球菌などのばい菌が繁殖し、黄色い膿の様なおりものが増え、臭いも不愉快な臭いに変わります。膣に炎症が起こるわけです。その刺激で、痒みが出たり、ヒリヒリ痛みがでたりする。これが、萎縮性膣炎といわれるものの実体です。
治療
治療の基本は不足している女性ホルモンを補うことであります。
これを、ホルモン補充療法といっています。
では、どういうふうにして不足しているホルモンを補うのかという問題ですが、一番普通のやり方は、口から飲む方法です。少量の女性ホルモンの錠剤を毎日飲む。 これには、現在2種類あって、作用の比較的弱いエストリオールという製剤と、もう少し作用の強いプレマリンという製剤があります。
また、月経の終わってしまった婦人がこれらの薬を飲み続けていると、ホルモンの作用で生理のような出血を見ることがあります。そういう場合は、同時に黄体ホルモンを一緒に飲むことによって不愉快な出血を防ぐことができます。
最近、新しいタイプのホルモン剤として、皮膚に貼って効く女性ホルモンというのが人気があります。直系2cm位の、軟らかい円盤状のフィルムですが、これをおなかとか腰に1日おきに張り替える。口から飲む場合には、胃腸障害を起こす人がいる。肝臓に負担がかかる。あるいは消化、吸収などでロスがある。それに対して、貼り薬は、直接皮膚から血管に吸収されるから、胃や肝臓に負担がかからない。薬が消化、吸収で効力が失われることはない、などの利点がある。
それからもう一つ、膣錠です。エストリオールを錠剤として、直接膣のなかに入れてあげる。今回のような萎縮性膣炎にはよく効きます。しかし、毎日とは言わないまでも、1週間に1~2回は、膣洗浄に通わなければならない、というわずらわしさがある。
こういう治療を続ける事により、膣の粘膜は厚くなり、細胞のグリコーゲンは増え、乾燥していた膣の壁は潤いを取り戻します。その結果、膣内は酸性を取り戻し、乳酸桿菌も増え、清潔になります。性交時の痛みも和らぎ、めでたしめでたしということになるわけです。
ここで、問題はこのホルモン療法をいつまで続けるべきかということです。
もともとからだのなかで作られるホルモンが不足して起こる症状ですから、外からホルモンを補充しなければ、一時的にはよくなっても、治療を止めれば、元の木阿弥で、症状は再発します。それですから、このホルモン補充療法はかなり長期間続けることになります。その場合の心配は、長い間ホルモン剤を使って副作用はないかということです。この点については、アメリカ、ヨーロッパが先進国で、20年以上前から積極的に、中高年女性に対するホルモン補充療法が行われ、膨大なデータが集まっています。それによりますと、子宮頚癌については、ホルモン補充療法をしている人と、していない人との間には発生率に差はないといわれております。乳ガンと子宮体癌では、女性ホルモン単独では、やや発生率が増える傾向にある。しかし、これに黄体ホルモンを同時に使用した場合では、逆に癌の発生率は下がったと言われております。黄体ホルモンには発ガンを抑える働きがあるわけです。
ホルモン補充療法には、萎縮性膣炎の治療に効果があるばかりでなく、もっと他にもすぐれた点があります。その2、3をあげてみますと、
第1、ホルモン補充療法を続けることにより、骨粗鬆症を予防します。
女性は更年期を境に、骨のカルシウムが急激に減少し、骨が弱くなります。この原因は、血液中の女性ホルモンが減少するからです。女性ホルモンを補うことにより、カルシウムの減少を抑えることができるのです。
第2に、女性ホルモンは、コレステロールの増加を防ぎます。閉経後、コレステロールの増加に悩まされている女性はたくさんいますが、補充療法を行うことにより、コレステロールをさげ、ひいては動脈硬化、脳卒中を予防することになります。いわゆる、生活習慣病の予防に役立つわけです。
3、これは、最近の研究ですが、ホルモン補充療法が、女性のアルツハイマー病に効果のあることがわかってきました。これは、京都府立大学の本庄教授らの発表ですが、アルツハイマーの患者さんに、女性ホルモンを継続して飲ませると、物忘れが改善し、計算力が増し、情緒も安定するそうです。
話は、萎縮性膣炎に戻りますが、一般に炎症があると痛みとともに機能障害が起こります。働きが悪くなるわけです。例えば、腸に炎症があると腹痛に伴って 下痢をします。膣に炎症があれば、痛みとともに機能障害として、性交痛、性交困難症が出てきます。
たとえ炎症に至らなくても、更年期になって生理が止まりますと、卵巣からのホルモンの分泌が少なくなり、膣粘膜が薄くなり、分泌物も少なくなって、性交痛、性交困難症が発生します。
そこで、萎縮性膣炎に伴う、さらにひろく更年期に伴う、性交痛、ないしは性交困難症についてお話を進めてみたいと思います。
この発生のメカニズムについては、さきほど申しましたように、女性ホルモンの不足によって、膣の粘膜が薄くなることと、潤いがなくなって乾燥気味になることがあげられます。
この性交痛がどれくらいの頻度で発生するかということについては、山形大学の廣井教授の調査をご紹介したいと思います。これは311名の婦人を対象にしたアンケート調査ですが、性交時に痛みを感ずる人の数は、40歳未満では、ほとんどの女性は痛みを感じませんが、50歳以上では、43%の人が痛みを感じます。60歳以上ではじつに90%の人が、性交時痛みを訴えています。これは大変な数だと思います。もし、これが本当だとすると、医者の前で、性交痛を訴える患者さんはそんなにおりませんから、大部分の人は、黙って我慢しているのではないかと思います。しかし、楽しかるべき、性生活が苦痛に変わるということは、QOL quality of life いわゆる、生活の質の向上、という観点から見れば、明らかに、生活の質の低下につながるものだと思います。
年齢を重ねるに従って、性的欲求、性的行動は低下します。 しかし、その低下の仕方には個人差があって一様ではありません。夫婦ともに、同じレベルであれば、たとえセックスレスでもお互いに不満はないわけで、これはこれで問題ないと思います。一方、中高年でも、活発に夫婦生活を営まれている方もおられます。これもお互い満足されているので問題ありません。
問題は、やはり、夫婦間にアンバランスのある場合で、その一つは、今回の症状のように、男性の欲求に女性が答えられないといった場合です。こういうケースにホルモン補充療法を行うことにより、乾燥した膣に潤いを与え、膣の壁を厚く丈夫にし、よりスムーズな性生活を送ることができます。 また分泌物が不足の場合は、ゼリーを使って補う方法もあります。
これと、逆の場合もあります。女性の欲求に男性が答えられない場合です。東邦大学の調査では、日本人男性のインポテンツの割合は、40歳台で20%、50歳台で40%、60歳台で60%と報告されております。最近、バイアグラという薬が発売されました。この薬は、性的不能の男性を回復させるという作用があり、中高年の男性に大いに希望を持たせる薬であります。しかし、考えてみればこういう男性のパートナーは女性であり、その恩恵を受けるのもじつは女性ではないか、とも考えられます。同じ東邦大学の泌尿器科では、夫がバイアグラを飲むことに同意した女性17組について調査しました。17組のうち11組が継続して薬を飲みたいと答えております。5組はどちらでもよい。そして、薬を飲むのは止めてほしいと言ったのはたった1組だけでした。バイアグラは男性だけに役立っているのではなく、男性を通してパートナーの女性にも恩恵を与えていることになります。
今や女性の平均寿命は80歳を超えました。閉経を50歳としますと、その後約30年間生きることになります。30年と言いますと、20歳で成人式を終えた若者が50歳の更年期を迎えるまでの長さです。この30年間をいかに生き甲斐のあるものにするかが課題であります。健康に健やかに生きると言った場合、性の問題も決して無視できないと思います。夫婦間の性生活にアンバランスの生じた場合は、日常生活その他の面でもしっくりいかないことが多いのではないでしょうか。
ホルモン補充療法や、バイアグラを上手に使うことは、性生活上のミスマッチを解決する一つの手段になるかと思います。いわゆるクオリティー・オブ・ライフ、生活の質の向上にこのような薬が役に立つのではないでしょうか。アメリカやヨーロッパでは、20年くらい前から、ホルモン補充療法が広く行われ、今では更年期にはいった女性の15ないし20%が常用しているといわれます。それに対して、日本ではここ数年やっと使われはじめましたが、まだ、更年期女性の1~2%程度の普及率です。はたして、日本でホルモン補充療法が欧米並みに普及するかどうか、私は注目して見ていきたいと思っております。
胚盤胞の移植
より生理的な状態に近い胚移植を
体外受精胚移植では通常採卵した後2日~3日目に子宮内に受精卵を移植します。しかし体外での胚の培養を数日延ばして、胚盤胞の時期になった時に移植する方法が最近行われるようになってきました。 元々卵管内で受精したあとは、胚盤胞の時期に子宮内に入ってくるので、この時期に胚移植を行う方がより生理的な状態に近いと言えます。
ただ今のところでは、胚をこの時期まで順調に成育される事にむずかしい時もあり、全てこの時期に胚移植を行うという所に至っておりません。
胚の培養方法を含めてまだいろいろ研究がなされている所です。
卵管鏡下卵管形成法(FT法)
自然な妊娠を望まれる方へ
卵管がつまっているために妊娠出来ない方は、最近体外受精を選択される方が多いのですが、卵管を正常の状態に直して自然の形で妊娠されたいという方も多く、そういう方のために幾つかの治療法が考えられております。
今のところ卵管がつまっている方(卵管閉塞症)の治療法にはいくつかの方法が考えられております。
(1) 検査をかねた方法ですが、卵管造影法(卵管のレントゲン撮影)、卵管通 気法(卵管内にガスを送る)あるいは卵管通水法(卵管内に水を送る)などが最初に行われるのが普通 です。
(2) お腹をあけて開腹手術(ミニラパといいます)、あるいは腹腔鏡下手術を行うことがあります。
(3) X線で観察しながら卵管内にチューブを入れて卵管を広げる方法があります。
(4) 子宮鏡を入れて子宮の内をみながら卵管の入り口をみつけ(子宮卵管口)ここからカテーテルといった細い管を入れます。この状態で水を入れて卵管の通 りをみます。同時に卵管が狭い時はこれを広げることが出来ます。これを子宮鏡下選択的卵管通 水法といいます。
(5) この他最近効果が比較的高く、注目をあびているのが卵管鏡下卵管形成術(FT法)です。
これは卵管の中に直接チューブを入れて卵管内につまっている部、狭くなっている部分をバルーンという風船の様なもので開く方法です。図のように狭くなっている部分にバルーンをあて、このバルーンをすすめる事で卵管の狭窄部を広げていく方法です。
この時は腹腔鏡を用いてお腹の中をみながら行う方法と、腹腔鏡を用いないでやる方法があります。
PCO(多のう胞性卵巣症候群)について
月経不順は代表的症状です
月経不順を訴えられて来られる方にPCO(多のう胞性卵巣症候群)という病気にかかっていると考えられる方がおられます。ここではそのお話を致しましょう。
PCO(多のう胞性卵巣症候群)という病気は、聞きなれない方が多いと思いますが、意外と多い病気です。月経不順で悩んでいる人のうち、約20%がこの病気の可能性があると考えられています。
この病気の原因はまだわかっていませんが、病状は比較的はっきりしています。無月経や稀発月経(まれにしか月経がおこらない)などの月経不順が、まず代表的な症状です。婦人科で超音波検査を受けると、卵巣の中の小さな袋(のう胞)がたくさん認められ、血液検査では脳下垂体というところからでるLH(黄体形成ホルモン)というホルモンの値が高くなります。
一方、目に見える症状として肥満、ニキビ、多毛といった、男性ホルモンがはたらきすぎたためにおこる症状もあります。また、不妊との関係も指摘されています。
ただ、日本人には肥満やニキビ、多毛などの症状がでるタイプは比較的少ないといわれています。もし今ご相談の方にこれらの症状がでていないのであれば、今後きちんとした治療を受けることで、そうした症状を防ぐのは可能だと考えられます。
治療については、赤ちゃんが欲しいという方とそうでない方とで差があります。PCOのために排卵がおこりにくく、赤ちゃんがなかなかできないという相談を受けることが多いので、そちらのほうから先にお話ししましょう。
治療法として(1)第一選択は排卵誘発剤です。クロミフェン(クロミッド)というくすりを用いますが、幸いこのくすりで高い排卵率が得られます(60%)。これで排卵がおこらないときは、排卵誘発剤の量 を増やしたり、血液中のホルモンの量を調べながらほかのホルモン剤を一緒に使ったりします。
それでも排卵がおこらないときは、(2)排卵誘発の注射を用いたり、(3)卵巣を電気メスやレーザーなどで切開する外科的な治療法もあります。しかし(2)と(3)はその効果 と副作用について医師と十分に相談することが大切です。
次に赤ちゃんを望まれていない方についてですが、この場合は、排卵誘発剤を積極的に使うのをおすすめしないこともあります。しかし、ホルモン剤(おもに女性ホルモン剤)を用いて、ある程度周期的に月経をおこさせることは大切です。くすりの副作用を感じるときは、ホルモンの種類や量 を調節してもらうことも可能です。